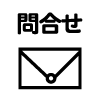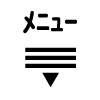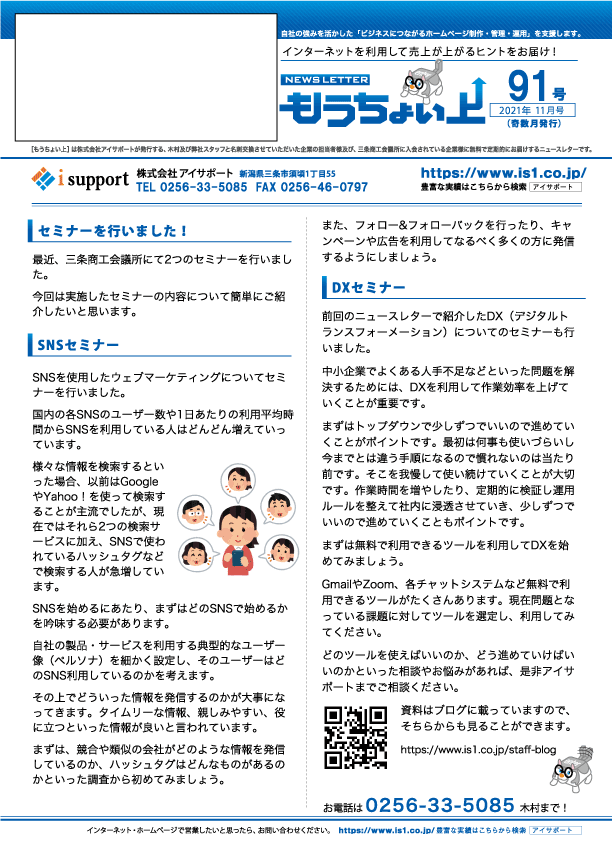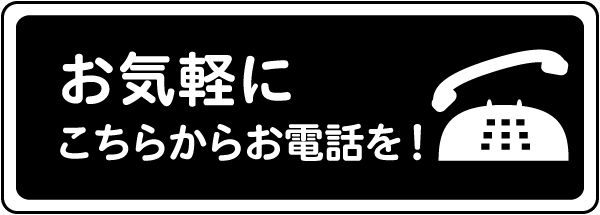新着情報
-

-
googleマイビジネスの使いかた
-
実店舗を持ちながらビジネスを行っているオーナーや企業の皆様、Googleマイビジネスを利用していますか?Googleマイビジネスは集客力に長けたツールです。
今回は、Googleマイビジネスを取り入れるべき理由や使い方についてご紹介していきます。Googleマイビジネスとは?
Googleマイビジネスとは、Google社が展開している、実店舗の宣伝やPRができるサービスです。登録するとGoogleの検索結果上位に表示されるようになります。GoogleマップやGoogle検索のユーザーに対して以下のようなことができます。
・店舗・企業の住所や電話番号、営業時間などを伝えられる
・ユーザーから口コミを投稿してもらって、店舗・企業の魅力を伝えられる
・キャンペーン情報や新商品情報などをアピールできる
Googleマイビジネスはユーザーの検索したエリアに応じて表示されるため、検索上位に表示されやすく、集客にもつながりやすいのが特徴です。
登録にも利用にも費用がかからないので、試しに登録して始めてみるということもできます。Googleマイビジネスをおすすめする理由
集客にGoogleマイビジネスをおすすめする理由として、Google検索を使って店舗を調べている人が多いというものがあります。Googleは日本でもっとも利用者が多い検索エンジンです。Google検索を利用する機会が多いということは、Googleの検索結果上位に表示されることが集客につながりやすいということになります。
そのほかにもGoogleマイビジネスにはインサイトという機能があり、ユーザーが利用した検索方法や検索数、写真の閲覧があったかどうかといったユーザーの行動などを知ることができます。インサイト機能を使えば店舗分析を簡単に行えるのも理由の1つです。Googleマイビジネスの使い方
Googleマイビジネスを始めるのはとても簡単です。
まず、Googleアカウントを取得してGoogleマイビジネスにログインします。
ログインしたら「店名」「業態」「住所」「営業時間・定休日」「年末年始などの特別営業時間」「電話番号」「店舗のホームページやSNS」「属性」「写真」といった基本情報を登録します。ここで登録した内容がGoogleで検索された際に結果として表示されるので、正しい情報をできるだけ詳しく載せましょう。写真は制限なく載せることができるので、店の魅力が伝わる良い写真をできるだけ多く載せておきましょう。
基本情報を登録後、オーナー確認を済ませたら編集した内容がWeb上に表示されるようになります。
Googleマイビジネスを始めたら、口コミ機能や上記で紹介したインサイト機能、新商品やサービスなどの情報を載せられる投稿機能を活用してさらに高い集客効果を狙いましょう。まとめ
インターネットで情報を集めることが当たり前になっている現在、インターネットでの集客は重要度が増しています。最多のユーザー数を誇るGoogle検索エンジンを使用するサービスなので、上手に活用すれば集客数を大幅に増やせるでしょう。
まだ始めていない方はこの機会にぜひGoogleマイビジネスを活用しましょう。
-
-

-
2021年12月:補助金・助成金最新情報
-
補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。
潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。
新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。補助金:「令和3年度 ものづくりWeb見本市等出展支援事業補助金」
市内中小企業等の新たな販路の開拓を支援するため、新型コロナウイルス感染症拡大を背景に必要性が高まっているWeb見本市等への出展、開催、これらのためのコンテンツ制作に係る経費の一部を補助します。
【対象者】
市内に事業所を有する中小企業者等
【対象事業】
①Web見本市等への出展(③と併用可)
②Web見本市等の開催(③と併用可)
③Web見本市等のためのコンテンツ制作(①又は②と併用可)
※来年度以降のWeb見本市等の出展、開催を前提としたコンテンツ制作も可
(今年度はWeb見本市等の出展、開催しない場合も可)
【支援内容】
上限額50万円
補助率3分の2以内
【実施機関】長岡市
【詳しくはこちら】https://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/webmihon.html令和3年度 IT・IoT・AI設備導入支援補助金
中小企業が、生産性向上などに取り組むため、新たなIT・IoT・AIシステムを導入する取得費の一部を支援します。
【対象者】
市内に事業所を有する製造業に該当する中小企業者等
【対象経費】
「ソフトウェア」、「センサー機器」、「生産性向上に資するシステム等の導入・開発経費」に該当する経費
※取得総額50万円以上を対象とする。
※単なるIoTオプションのついた工作機械は対象外とする。
※現状のシステムをバージョンアップするだけ等、生産性向上に繋がらないシステムは対象外とする。
※はん用的な事務用機械(事務用パソコン・プリンター等)は対象外とする。ただし、申請事業に用途を限定する備品(タブレット端末や大型ディスプレイ等)は対象とする。
※長岡市IoT推進ラボの個別相談を受けることを必須とする。
【支援内容】
上限額100万円
補助率3分の2以内
【実施機関】長岡市
【詳しくはこちら】https://www.city.nagaoka.niigata.jp/sangyou/cate03/hojyokin/setsubi.html令和3年度:オンラインによる非接触型海外展開支援事業
NICO(公益財団法人にいがた産業創造機構)では、新型コロナウィルス感染症の影響により、現地への渡航を伴う営業活動や販促活動が困難となっている中で、渡航せずに行う、越境ECによる販売活動やオンライン商談による販促活動の経費の一部を助成します。
【概要】
(1) 越境EC参入事業
越境ECサイトの構築、越境ECモールへの出店、自社越境ECサイトへの誘客を目的としたWEB上でのプロモーション活動に要する経費の一部を助成します。
(2) 動画・画像コンテンツ制作事業
海外とのオンライン商談等で使用するための動画・画像コンテンツ制作に要する経費の一部を助成します。(海外展開を目的としたオンライン見本市、オンラインによる商談に使用する動画・画像を対象とします。)
【対象者】
中小企業者
【支援内容】
上限額200万円
補助率2分の1以内
【実施機関】公益財団法人にいがた産業創造機構
【詳しくはこちら】https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/48508/令和3年度:データ利活用型設備導入助成金
NICOでは、AI・IoTを活用したシステム・機器等を導入する等により、データ収集・分析等を通じて、生産性や付加価値の向上を図る県内中小企業のモデル的な取組を支援します。
【対象者】
新潟県内に本社又は事業所、工場を設置している中小企業者
【対象事業】
AIやIoTを活用したシステム・機器等を導入する等により、データ収集・分析等を通じて付加価値向上が期待できる県内中小企業者のモデル的な取組
【支援内容】
上限額250万円
補助率2分の1以内
【実施機関】公益財団法人にいがた産業創造機構
【詳しくはこちら】https://www.nico.or.jp/sien/hojokin/48258/まとめ
新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。
※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。
-
-

-
いろいろなチャットツールの紹介
-
昨今、デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉を頻繁に耳にするようになりました。デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、進化したIT技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させるという概念のことです。
今回は、DXツールのひとつでもあるチャットツールについてご紹介いたします。チャットツールについて
Slack
SlackはSaaS型のビジネスチャットツールです。Slackにはチャンネルという機能があり、途中からそのチャンネルに入った人でも過去の会話のログを追うことができるため、それまでの経緯を把握することができます。
その他にも通知を細かくカスタマイズできたり、過去のメッセージを検索できたりもします。ファイルのアップロードやダウンロード、ファイルのプレビューなども可能になっています。また、Googleカレンダーといった外部サービスとの連携も可能です。
公式サイト:https://slack.com/intl/ja-jp/Chatwork
Chatworkとはビジネス利用に特化したチャットツールです。Chatworkはチャットワークユーザーであれば、社内外問わずにすぐチャットでやりとりをすることが可能です。また、大企業や官公庁も導入できるほどのセキュリティ水準を保っています。
チャット機能をはじめ、ファイル共有機能やタスク管理機能、ビデオ通話(音声通話)機能など、ビジネスシーンにおける利用をスムーズに進めるための機能が充実しています。Slackと同様、外部サービスとの連携も可能です。
公式サイト:https://go.chatwork.com/ja/LINE Works
LINE Worksは仕事で使えるビジネス版LINEです。LINE WORKSはLINEとは別のアプリですが、LINEのユーザーインターフェイスを踏襲しているため、使い方も似ており誰でもすぐに使い始められるのが特徴です。
LINEのトーク機能との主な違いは、既読数だけでなく「誰が読んだか」までわかるところです。社内アドレス帳を作成することができ、各部署や拠点ごとのメンバーを一覧表示することも可能です。社外のLINE WORKSユーザー・LINEユーザーともやりとりができます。
公式サイト:https://line.worksmobile.com/jp/Microsoft Teams
Microsoft Teamsは「Microsoft」が提供しているビジネスチャットツールです。Teamsを導入する最も大きなメリットして、ビジネスアプリの定番Word、Excel、PowerpointといったOfficeアプリとの連携が可能なところです。Teams上でこれらOfficeアプリを起動すると、ファイルの閲覧だけでなく共同編集も可能になるため生産性が上がります。
Teamsにはチャットだけではなく、通話、ビデオ会議といった複数のコミュニケーションツールが実装されているため、利用する機能により別のツールを立ち上げる必要がありません。
公式サイト:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-softwareWorkplace
Workplaceは「Facebook」が提供しているビジネスチャットツールです。facebookの画面や仕様をそのまま活用し、ビジネスでの用途や要望に応えるさまざまな機能を詰め込んだビジネス用SNSです。
Facebookでは友達になったユーザーの投稿などを見ることができますが、Workplaceでは逆で社内メンバー全員の投稿がどんどんタイムラインに入ってくるため、いつでも見ることができます。「公開」「非公開」「秘密」といった3種類のグループを作成することができるため、各案件毎に情報共有することができます。
公式サイト:https://ja-jp.workplace.com/まとめ
今回はいろいろなチャットツールについてご紹介いたしました。
ビジネスチャットの導入を検討する場合、「Slack」「Chatwork」「Microsoft Teams」の主要3ツールのうち、何を選んだらいいかを検討するのがベストです。ツールごとにどのような機能があるのかを把握し、その上で、「現場で使いやすいもの」「セキュリティに長けたもの」「コストの安いもの」など細かい要望に合わせて、それ以外のツールについて検討するようにしましょう。
-
-

-

-
いろいろなオンラインストレージの紹介
-
昨今、デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉を頻繁に耳にするようになりました。デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、進化したIT技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させるという概念のことです。
今回は、DXツールのひとつでもあるオンラインストレージについてご紹介いたします。オンラインストレージについて
firestorage
月間800万人以上の人に利用されている大容量ファイルを簡単に共有できる無料オンラインストレージです。会員登録不要の無料プランでも容量無制限で利用できます。
無料プランの場合、1ファイルあたり最大2GiB(1GiB=1,024MB)までという制約はありますが、総容量は制限されていません。容量を気にすることなく1度に複数のファイルをアップロードできるので、スムーズにデータを共有することができます。
公式サイト:https://firestorage.jp/GoogleDrive
Googleドライブとは、Googleが提供しているオンラインストレージサービスです。Googleドライブにデータを入れることでPCやスマホなど複数のデバイスからアクセスすることができます。
また、共有機能で複数の人とのデータのやりとりも可能です。アップロードだけでなく、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートを使用することでドライブ上で直接データを作成することも可能です。
公式サイト:https://www.google.com/intl/ja_jp/drive/OneDrive
OneDriveとは、Officeファイルはもちろんのこと、写真や動画など様々なデータファイルをオンライン上に保存できるオンラインストレージサービスです。Microsoftアカウントさえあれば、無料で使用できます。
Officeアプリで作成したファイルをOneDriveフォルダに格納すれば、複数のデバイスや他の人ともファイルを共有できます。共有することでファイルを見る・操作する・ダウンロードする、といったことが可能になります。更に、インターネット上のOneDriveにアクセスするのではなく、パソコン内のフォルダ一覧からOneDriveを選択して、ローカルアカウントにてファイルを閲覧・編集することもできます。
公式サイト:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storageDropbox
Dropbox(ドロップボックス)とは、インターネット上でファイル管理や共有を行う、「クラウドストレージサービス」です。Dropboxでは、インターネット上に全てのデータを保存するので、PCやUSBが盗難に遭ったり紛失したりしてしまってもデータを失うことはありません。Dropboxは、ファイルや写真などのデータ容量の合計が「2GB」まで無料で保存することができます。
ユーザー間でのファイル共有や、誤ってファイルを削除してしまっても30日間、もしくは180日間ファイルがゴミ箱に残るので、復元することが可能です。
公式サイト:https://www.dropbox.com/ja/まとめ
今回はいろいろなオンラインストレージについてご紹介いたしました。
オンラインストレージをうまく活用すれば、これまでより企業の生産性を高めることができます。運用の仕方を従業員に周知徹底しておくと、導入の効果は高まりやすいです。そのためには、事前にサービスごとのメリットや機能を理解した上で導入するサービスを選択する必要があります。自社に最適なものを選ぶために、選定のポイントをしっかり把握しておきましょう。
-
-

-
いろいろなMAツールの紹介
-
昨今、デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉を頻繁に耳にするようになりました。デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、進化したIT技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させるという概念のことです。
今回は、DXツールのひとつでもあるMAツールについてご紹介いたします。MAツールについて
マルケト
マルケトは、「BtoB」「BtoC」問わずに、全世界5,000社以上で利用されているMAツールです。自社の商品やサービスにあう顧客層を決定するターゲティング、メールの作成や配信を行うメールマーケティング、ソーシャルメディア連携、ランディングページやフォームの構築など多種多様な機能を備わっています。
収集したデータからユーザーへのデジタル広告を自動最適化することで、より緻密なターゲティングを実現し、無駄な広告コストを下げたり、SEOに最適化されているかグラフ化しており、設定したキーワードで自社サイトの順位を把握したりすることも可能です。
公式サイト:https://jp.marketo.com/Salesforce Pardot
Salesforce Pardotはセールスフォースが提供する「BtoB」向けのクラウド型MAツールです。BtoBマーケティング機能が充実しており、トラッキング機能とスコアリング機能によって、高い確度で商談につながりやすいリードを追跡し、有望な見込み顧客を抽出することができます。
Salesforceと連携して使えるMAツールであるため、あわせて使用することで蓄積された顧客情報をスムーズに連携できます。これにより、効果的なセールス活動・マーケティング活動が行えます。
公式サイト:https://www.salesforce.com/jp/products/pardot/overview/ZOHO CRM
Zoho CRMは、世界15万社で活用されているクラウド型のCRMです。Zoho CRMには、「Zia(ジア)」と呼ばれるAIが搭載されており、どの顧客を重点的にアプローチすべきかの提案やいつ電話をかければつながりやすいか、顧客ごとに時間帯を示すといったアドバイスを受けることができます。
電話やメール、議事録等の文書も一元管理できるため、コミュニケーション内容を記録するだけでなく、Zoho CRMから直接発信や受信を行えます。
公式サイト:https://www.zoho.com/jp/crm/feature/marketing/SATORI
「SATORI」は、顧客開拓を自動化するマーケティングオートメーションツールの代表的な製品です。これらのマーケティングオートメーションツールの機能の中でも、SATORIは、Webサイト上のコンバージョンを促すことやリードの購買意欲を高め、自動的にアプローチすることが可能です。
お問い合わせフォームや資料ダウンロードフォームなどを簡単に作成することができ、常設フォームだけでなく、SATORIで可能となるポップアップフォームを利用することで、見込み顧客により有効にアプローチすることが可能です。サイトを閲覧したターゲットの行動履歴に基づいて、表示するコンテンツを最適化することも可能です。
公式サイト:https://satori.marketing/まとめ
今回はいろいろなMAツールについてご紹介いたしました。
MAツールにはいくつかの種類がありますが、企業によって必要となる機能は異なります。BtoBあるいはBtoC事業向けであるかどうかをはじめ、集客や誘導、分析の有無、顧客育成などさまざまな特徴があるため、機能の必要性を見極めることが大事です。自社の用途やニーズに応じて比較検討しましょう。
-
-

-
アイサポートで使っているDXツールの紹介
-
昨今、デジタルトランスフォーメーション(DX)という言葉を頻繁に耳にするようになりました。デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、進化したIT技術を浸透させることで、人々の生活をより良いものへと変革させるという概念のことです。
今回は、DXの取り組みにおいて弊社で実際に使用しているツールについてご紹介いたします。チャットツール
以前はメールでのやりとりが主でしたが、やりとりが多いところはチャットを利用させてもらっています。メールですと、前後の文章を読みながら経緯を理解するのに時間がかかる場合もありますが、チャットだと比較的分かりやすくなります。
また、余計なCCなど入れなくても関係者に情報が届きますし、挨拶文も不要なのでいろいろと時間の短縮にも繋がります。Slack
SlackはSaaS型のビジネスチャットツールです。Slackにはチャンネルという機能があり、途中からそのチャンネルに入った人でも過去の会話のログを追うことができるため、それまでの経緯を把握することができます。その他にも通知を細かくカスタマイズできたり、過去のメッセージを検索できたりもします。また、Googleカレンダーといった外部サービスとの連携も可能です。
公式サイト:https://slack.com/intl/ja-jp/Chatwork
Chatworkとはビジネス利用に特化したチャットツールです。Chatworkはチャットワークユーザーであれば、社内外問わずにすぐチャットでやりとりをすることが可能です。また、大企業や官公庁も導入できるほどのセキュリティ水準を保っています。Slackと同様、外部サービスとの連携も可能です。
公式サイト:https://go.chatwork.com/ja/MAツール
MAツールはメルマガの配信と顧客管理がセットになっているようなツールです。興味ある人を見える化できるという便利なシステムです。4、5年前から取り組み活用しているツールです。
マルケト
マルケトは、「BtoB」「BtoC」問わずに、全世界5,000社以上で利用されているMAツールです。自社の商品やサービスにあう顧客層を決定するターゲティング、メールの作成や配信を行うメールマーケティング、ソーシャルメディア連携、ランディングページやフォームの構築など多種多様な機能を備わっています。
公式サイト:https://jp.marketo.com/Salesforce Pardot
Salesforce Pardotはセールスフォースが提供する「BtoB」向けのクラウド型MAツールです。BtoBマーケティング機能が充実しており、トラッキング機能とスコアリング機能によって、高い確度で商談につながりやすいリードを追跡し、有望な見込み顧客を抽出することができます。
公式サイト:https://www.salesforce.com/jp/products/pardot/overview/オンラインストレージ
メールで大量のデータを送るときに使用します。
firestorage
月間800万人以上の人に利用されている大容量ファイルを簡単に共有できる無料オンラインストレージです。会員登録不要の無料プランでも容量無制限で利用できます。無料プランの場合、1ファイルあたり最大2GiB(1GiB=1,024MB)までという制約はありますが、総容量は制限されていません。容量を気にすることなく1度に複数のファイルをアップロードできるので、スムーズにデータを共有することができます。
公式サイト:https://firestorage.jp/GoogleDrive
Googleドライブとは、Googleが提供しているオンラインストレージサービスです。Googleドライブにデータを入れることでPCやスマホなど複数のデバイスからアクセスすることができます。また、共有機能で複数の人とのデータのやりとりも可能です。アップロードだけでなく、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートを使用することでドライブ上で直接データを作成することも可能です。
公式サイト:https://www.google.com/intl/ja_jp/drive/その他
Zoom
Zoomとは、いつでも、どこでも、どんな端末からでも Web会議を実現するクラウドサービスです。映像や音声を使ってビデオ会議や電話会議が可能です。Zoomは遠隔会議、遠隔セミナー、遠隔授業向けクラウドビデオ会議サービスとして世界中で利用されています。
公式サイト:https://explore.zoom.us/ja/products/meetings/Salesforce
Salesforceとは、「顧客管理システム」です。営業活動をはじめ、問合せ対応やマーケティングなど、さまざまな場面における顧客情報をまとめて管理することができます。Salesforceは、「営業」や「マーケティング」など業務別で使えるさまざまな製品・サービスを提供しています。
5年前に導入し、アイサポートの中核のシステムといえます。
公式サイト:https://www.salesforce.com/jp/Googleカレンダー
Google カレンダー はGoogle Workspace の機能の1つで、クラウド上でスケジュールを管理できるサービスです。クラウド上で管理されるため、 Google アカウントにログインさえすれば、OSを問わず同じように利用することができます。そのためPCだけでなくスマホやタブレットでも利用できます。Gmailを始め、他のGoogleサービスとの連携も可能で、予定を簡単に共有することができます。
公式サイト:https://workspace.google.com/intl/ja/products/calendar/まとめ
今回は弊社で実際に使用しているDXツールについてご紹介いたしました。DXツールといっても様々なものがありますので、自社に合ったものを選ぶようにしてください。まずはお試しで無料体験できるツールもありますので、使ってみたいというものがあれば是非実際に利用してみてください。
-
-

-
SEO対策に便利なチェックツールについて
-
ウェブサイトの運営をする場合、検索サイトで特定のキーワードを打ち込んだときに検索結果の上位に表示されるように、コンテンツを工夫する努力が求められます。検索結果の上位に表示されるようにするにはSEO対策が欠かせません。
より効率的にSEO対策を行えるようにサイトの内容をチェックし、必要な改善策を指摘してくれるチェックツールが存在します。
今回は、SEO対策に便利なチェックツールについてご紹介していきます。SEOとは?
SEOとはサイトを訪れるユーザーに価値のあるコンテンツを提供し、検索エンジンにコンテンツが高品質とみなされるようにページ内容を最適化することです。
日本で利用されている検索エンジンのシェアとしては、Googleが全体の70%以上を占めているため、Googleがどのような基準で検索結果の順位をつけるのかをきちんと把握し、適切に対応していく必要があります。SEO対策に便利なチェックツールとは?
検索エンジンの基準に従いながら良質なコンテンツを考えるのは、手間がかかるし難しいです。そこでSEOチェックツールを活用すれば、初心者であっても簡単にSEO対策を行うことができます
SEOチェックツールとは、現状のSEO対策における問題点を把握し、必要となる施策を明確化してくれるツールです。サイトの更新や管理を行っているだけでは「なぜ検索上位に表示されないのか分からない…」といった状況に陥ることも少なくありません。
そのような場合にチェックツールを活用することで、問題点の所在を捉え、必要な改善策が何かを認識できるようになります。SEOチェックツールでできること
SEOチェックツールでは検索順位のチェック、競合サイトの分析、コピペチェックなどを行うことができます。
・検索順位のチェック
SEO対策を行う上で、設定しているキーワードにおいて、自社サイトの検索順位が日々どのように変動しているのかを瞬時に行うことが可能です。
・競合サイトの分析
競合サイトを分析するSEOツールでは、自社サイトよりも検索上位に位置する競合サイトのコンテンツを分析し、競合サイトに含まれていて自社サイトに含まれていない要素をチェックできます。
・コピペチェック
自社サイトに掲載しているコンテンツが、検索エンジン側によって他のサイトのコピーだとみなされてしまうと、サイトの信頼性が失われ、検索順位が下がってしまう恐れがあります。コピペチェックを行ってくれるSEOツールは、他サイトとの類似性の程度などを自動で診断してくれます。まとめ
検索エンジンで上位表示を狙うことが、サイト運営の目的を達成する上でとても重要です。その際にポイントになるのが、効果的なSEO対策を行っているかどうか、という点です。SEO対策を行う上で有用となるのがチェックツールです。今回紹介した以外の機能もありますので、興味があれば弊社までお問い合わせいただければと思います。
-
-

-
営業に効果的なBtoB向けメルマガ活用術!
-
メルマガは、約20年も前から多くの人に認知されている営業ツールです。メールによる販促はマーケティングオートメーションを利用した配信などで、受注率のアップに貢献しています。しかし、営業の成果をあげるメルマガを作り出すのは、簡単なことではありません。特にBtoBにおいてはメルマガでの営業が難しいという声を聴くことがあります。
今回は、営業に効果的なメルマガの作成方法や配信についてご紹介いたします。現在のメルマガについて
最近はビジネスチャットツールを使ったコミュニケーションが活性化し、メールの受信数が昔よりも減っていると感じることもあるかもしれません。以前であれば、忙しいビジネスマンほど、メーラーには様々なメールが溢れていて、メルマガが埋もれてしまう可能性が高かったと言えます。しかし、メールの受信数が少なくなれば、それだけメルマガをターゲットに認知してもらえる可能性が高くなってきます。また、スマホを利用して社外でもメールを確認する人もいるので、メルマガがターゲットに触れるチャンスも少なくはありません。今だからこそ、メルマガに有利なビジネス環境になっていると思われます。
営業に効果的なメルマガの作り方
BtoBの営業に使うメルマガは、BtoCと違いターゲットは法人です。そのため「信頼性」や「実績」が重要になってきます。次の各ポイントを押さえてメルマガを作成してみましょう。
ターゲットを想像する
まず、メルマガを読む人がどのような人なのかターゲットを明確にしましょう。ターゲットがメルマガを受け取り、商品やサービスの購入までどのようなアクションをするのか、社内ではどのような検討を経て購入に至るのかなどを想定することが大事です。
リストを整える
BtoBの営業をメルマガで行う際、配信リストは成果に影響を与える重要なものになっています。営業活動でコンタクトを取った見込み客、過去に取引歴があった会社など様々な配信先がありますが、これらのターゲットを1つにまとめて、メルマガを送ってしまうと、内容がターゲットの立場にマッチしない場合があります。自社とターゲットの関係をもとにリストを分けて、各々に合ったコンテンツづくりをしましょう。
メルマガのゴールを想定する
メルマガ作成の際に時々耳にするのは「ネタがない」という言葉です。これはメルマガを配信することが目的になってしまっている場合に出てくることが多くあります。メルマガの目的は何かを、作成に関わるすべての人が理解しておきましょう。
サービスの無料体験に申し込んでくれることがゴールなのか、それとも製品を実際に購入してもらうのがゴールなのか…決めたゴールに向かってどのようなプロセスを踏めばターゲットが興味を示すのかを想定してコンテンツを作成しましょう。見逃しにくい件名をつける
ターゲットと御社の付き合いが浅い場合、差出人が御社であることがわかっても、メルマガはスルーされてしまう可能性が高いです。受信メールのタイトルを見るのは一瞬ですので、メルマガを開封してもらうためにもメリットが一目でわかるような件名をつけましょう。
コンテンツには事例紹介を入れる
BtoBの営業の場合、顧客が重視する要素に「評判」や「実績」があります。他社でどのような成果をあげた商品なのか、購入した顧客はどのような感想を持っているのかなどが分かるようにお客様の声となる商品やサービスに関する感想を紹介しましょう。
配信のタイミングを考える
せっかく練り上げたコンテンツを用意しても、ターゲットに読んでもらえなければ意味がありません。ターゲットのライフサイクルをイメージして配信する時間帯を考えましょう。
BtoBの場合、午前中の時間帯を避けるのは一つの考え方です。他には、昼食が終わり午後の仕事に入る前の昼休みの時間に読んでもらうという考え方もあります。これらはあくまでも理想的な配信時間の一つです。実際にメルマガを何度も配信し、開封率などの調査を行い、自社のターゲットにとって最適な時間帯を検証しましょう。配信後について
メルマガを送信したら、効果検証を必ずしましょう。
開封率、メルマガのリンクからWebサイトにアクセスした数、コンバージョンに至った数などを調査して課題を明確にし、改善していくことが大切です。ABテストを行うなど、検証を重ねてメルマガ営業を行いましょう。
また、メルマガのツールですと開封率が分かりますがマーケティングオートメーションツールなら、個別のアクセス状況が分かりますのでおすすめです。まとめ
メルマガは「伝える」を大切に何度も挑戦することが大切です。どのようなセールスアプローチにも言えますが、はじめて挑戦して簡単に利益を生み出せるものはありません。メルマガというコンテンツを使いますが、実際はメルマガを書く人と読む人のコミュニケーションです。「伝える」という気持ちを大切にして、メルマガ配信にトライしていきしょう。
-
-

-
メルマガは今どう読まれているのか?日本のメルマガ購読について
-
2020年から続くコロナ禍によって、顧客へ直接メッセージを届けることができるメールマガジンの重要性はますます高まっています。そこで「メールマガジンがどの様に読まれているのか?」についてご紹介していきたいと思います。
調査内容について
調査目的
メルマガ購読状況についての現状を把握し、メール配信の企画・実務に携わる方々に役立つ情報を提供するため。
調査概要
・調査方法 :インターネット調査
・調査期間 :2021年3月24日〜4月25日
・対象者 :会社員、公務員、自営業を含めた経営者、20代〜60代(回答者の年齢分布は国勢調査の人口比率に対応)
※株式会社ベンチマークジャパンによる調査結果メルマガ購読についての調査結果
メルマガ購読の調査結果について、抜粋してご紹介いたします。
74.9%の回答者がメルマガを最低1通以上受信。仕事用・プライベート用メールアドレスの両方で、Gmailでのメルマガ購読が1番多く、仕事用・プライベート用共に、1日に平均1通〜5通のメルマガを読んでいる人が最も多い。
メルマガに期待するコンテンツの1位は「最新情報、ニュース」となっていました。
メルマガを受信している人は、世代別にどれくらいの割合なのか、という調査では全体では74.9%がメルマガを最低1通以上受信しており、世代別では年齢層が高いほど購読率が高いという結果になりました。世代が上になるほどメールアドレスの保有期間が長いことに加え、若い世代ほど情報収集チャネルがメールとSNSやチャットツールに分散していることが世代間の違いに影響しているのかもしれません。Q.メルマガを読むのはどの時間帯が多いですか?
仕事用メールアドレスの場合、1位は「12時~15時台」で26.6%、2位は「~9時台」で21.2%、3位は「10時〜11時台」で14.4%であり、BtoBのメルマガでは朝から午後までが読まれやすい時間帯であることが分かりました。これらは多くの方にとっての勤務時間中に読まれていることが考えられます。
一方、プライベート用メールアドレスの場合、1位は「21時~23時台」で33.4%、2位は「19時~20時台」で19.2%、3位は「12時〜15時台」で18.1%と、お昼~午後、夜の時間帯が読まれやすい時間帯であると分かりました。夜に関しては帰宅後のプライベートな時間に、お昼~午後に関してはお昼休みなどにメールをチェックしていることが考えられます。Q. 1日に平均何通のメルマガを受信していますか?
仕事用の1位は「1〜5通」である一方、プライベート用の1位は「21通以上」という結果になり、プライベート用メールアドレスの方が受信通数が多いことが分かりました。これは、そもそものメールアドレスの用途の違いに加え、会社のメールアドレスは転職などによって変わる(消滅する)ことも影響しているかもしれません。
Q. 購読しているメルマガの配信頻度は平均どのくらいが理想ですか?
仕事用・プライベート用共に1位は「週に2〜3通」、2位は共に「週に1通」という結果になりました。全体の2割程度が週1通未満を望んでいる一方、毎日を望む人が1割以上いるなど分散しており、理想的な頻度はメルマガの種類によって大きく異なると考えられます。
詳しくは以下のURLよりご確認ください。
まとめ
メルマガを配信する上で、実際にメルマガはどんな風に読まれているのか、どんな年代の人々が読んでいるのかといった情報を収集することはとても大事になってきます。
日々情報収集を行い、お客様に興味を持って読まれるメルマガを配信していきましょう。
-
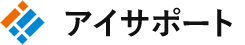
![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)