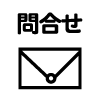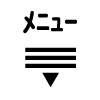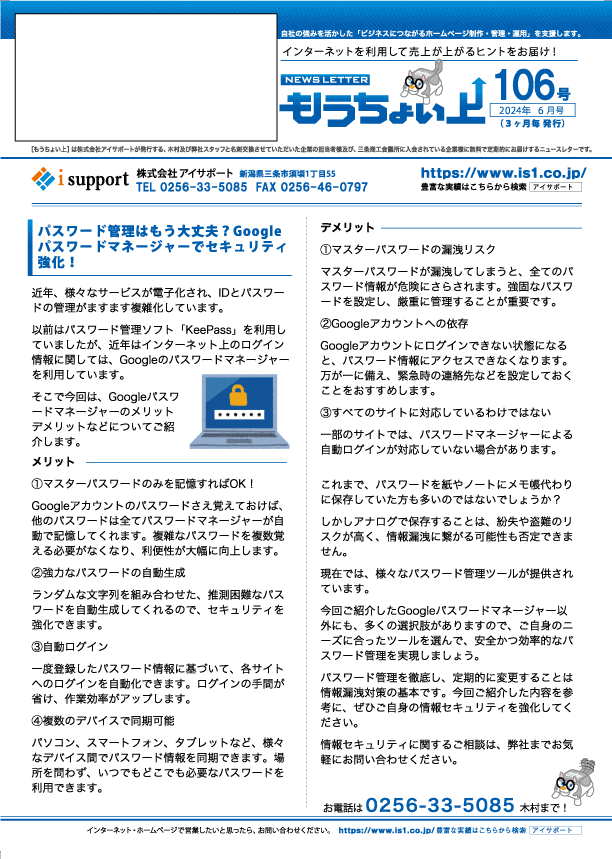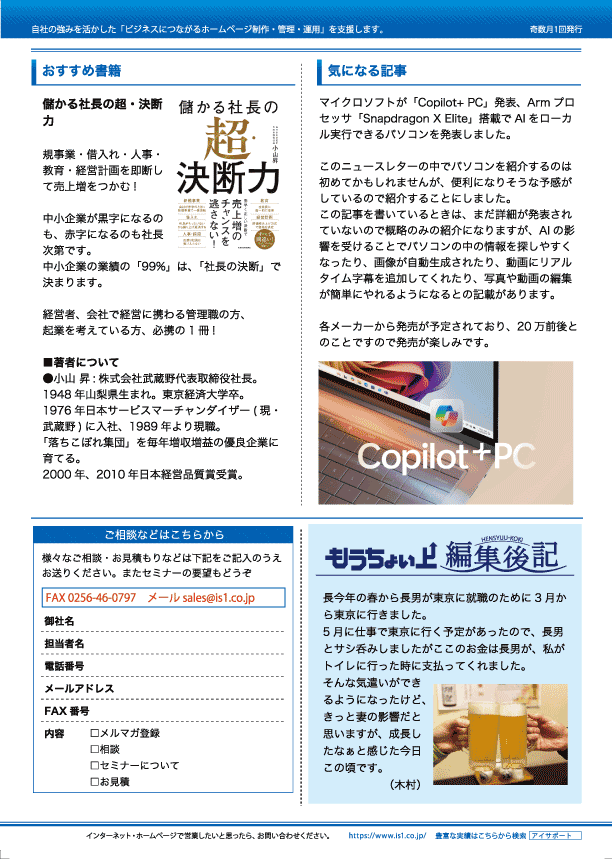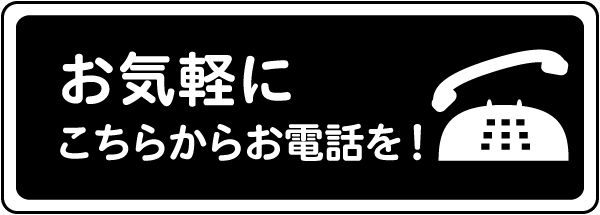新着情報
-

-

-
メールを間違って送ってしまった!メール誤送信対策について
-

今や電子メールは業務に欠かせないツールです。業務中にメールでたくさんの企業とやりとりしていく中で、誤ってメールを送信してしまった、なんてことありませんか?
メールの誤送信は「人為的に誤ってメールを送ってしまう、もしくは誤った内容のメールを送ってしまうこと」で、情報漏えいにより実際に被害が出て賠償問題に繋がってしまうような重大なミスと、認識不足や操作の間違いで起きてしまうマナー違反の2種類に分けられます。
今回はメールの誤送信対策についてご紹介させていただきます。メールの誤送信が発生する原因
メールの誤送信を防ぐために「なぜ誤送信が起きてしまうのか」、メール誤送信の原因を知ることが大切です。
【メールの誤送信のよくある失敗(一例)】
・「Bcc」のつもりが「To」「Cc」で一斉配信
・宛先間違い
・添付ファイル間違い
・添付ファイル忘れ
・書きかけのメールを送信
・敬称の未入力
など
社員のPC操作能力や、インターネットリテラシーに関する知識が一律であるとは限りません。
導入しているメーラーの機能について詳しく知らずに、適当にメールを送ってしまうことでも誤送信は起こります。また、送信前の確認作業が甘い社員もいます。メールのどこをチェックすればいいのか、全くわかっていないことがあるため、メールに関する社内ルール作りを行い、周知させることが大切です。
メールの誤送信を防ぐための対策方法
誤送信対策は、インターネット経由であらゆる情報がやりとりされる現代においては、もはやすべての企業が必ず取り組むべき課題であり、事業を営む上での当然の社会的責任の一種です。
誤操作や認識不足に起因する人的ミスにより発生する誤送信は「運用による対策」だけでは完全に防ぐことができず、ミスを未然に防ぐための「システムによる対策」もとる必要があります。
メールの誤送信を防ぐための3つの対策方法をご紹介します。社内ルール作りと教育
誤送信を防ぐ対策として、企業の規模に関わらず、メールに関するルール作りを行うことをおすすめします。
【メールに関する社内ルールに含めたい内容】
・メールを送る手順
・メールの送信種別の設定(TOやCC、BCC)
・件名の命名ルール
・添付ファイルの送信方法
・メールを送る前に使用するチェックリスト
・誤送信をしてしまった場合の対応
など業種や業務内容に合わせて、メールの社内ルールを作ることが大切です。作成したルールは社内の共有ファイルとして扱い、メールを扱う全社員が確認できるようにするとよいでしょう。
メーラーの設定を見直す
一般的に業務に使用されるメーラーには、特殊なツールを入れなくても誤送信を防ぐための何らかの設定項目があります。
送信保留機能や送信取り消し機能、宛先確認機能など、特別なツールを入れなくても、誤送信を防止できる機能が設定できるメーラーもありますので、一度使っているメーラーの設定を見直してみてはいかがでしょうか。ツールを導入する
残念ながら、社内ルールを制定しても、メーラーの設定を見直しても、ヒューマンエラーがゼロになることはありません。
さらなる誤送信対策を行いたい場合は、有料のツールを導入するのもひとつの手です。【メールの誤送信対策に使えるツールの機能(一例)】
・操作を間違えないためのシンプルなメール画面
・誤送信をしてしまった際にすぐに添付ファイルを削除する機能
・送信条件に合格しなかったメールの送信を止める機能
などツールを導入すれば費用がかかりますが、情報漏洩事故を起こしたときに想定される損害額と導入費用、月額費用を比較して検討してみてもいいかもしれません。
メールを誤送信してしまった場合の対処法
メールを誤送信してしまった場合は、直ちに対策を取ることが大切です。
対策の手順は社内ルールに従うのがベストですが、ルールがない場合は以下の内容を参考にしてみてください。・送信先に電話連絡を入れる
・電話がつながらなかったらメールでお詫びする
・メールや添付ファイルを削除してもらうようにお願いする
・上長やチームに誤送信をしてしまったことを共有またメールの誤送信に気づいた場合は、すぐに送信先に連絡を入れましょう。
まとめ
メールの誤送信を防ぐためには、社内ルールをきちんと作り、チェック体制の見直しをすることが大切です。
安全にメールを利用するために、誤送信だけではなく、添付ファイルの送り方や迷惑メールの見分け方などについても覚えておくとよいと思います。
もし誤送信対策のツールを導入したい、メールについてよくわからないことがある、などといったことがありましたら、お気軽にアイサポートまでご相談ください。
-
-

-
Googleハッシュタグ検索が日本独自の機能として正式リリースされました
-

Google日本法人は6月19日、「ハッシュタグ(#)」を使った検索が可能になったと発表しました。
ハッシュタグの後が日本語となっていれば、Google検索サービスで利用できるとしています。例えば、「#チョコレート」の検索結果には、動画やブログ、SNSなどの媒体から得られた情報が表示されます。Google Japan Blogでは「最新のトレンドや自分の興味や関心のあるトピックを深掘りして知りたいというニーズがより強い」ことが分かったと紹介した上で、流行や共通の話題を調べるのにハッシュタグがよく使われていると説明しています。
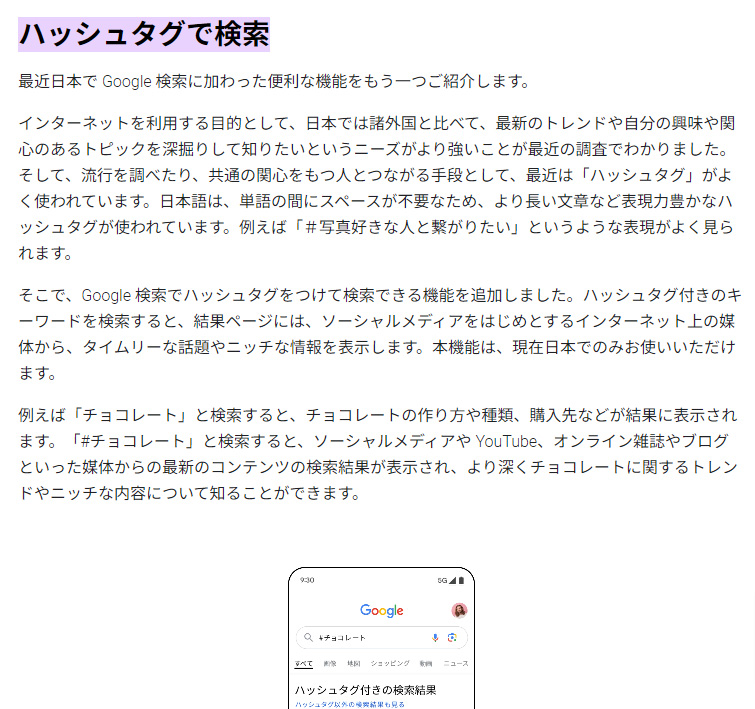

一般的に、通常の検索では関連性が最優先されます。
これに対してハッシュタグ検索では、ソーシャルメディアや YouTube、オンライン雑誌やブログなどから最新のコンテンツの検索結果を表示するため、トレンドやよりニッチな内容をユーザーは知ることができるとのことです。
つまり、タイムリーさがより重要視されます。なお、電話番号やプログラミング、カラーコード(Webブラウザなどの色表示指定)など、#(シャープ)を使ったキーワードの通常検索に悪影響を及ぼさないようにする仕組みも導入しているとのこと。
ぜひ実際にPCやスマホで「#」をつけて検索してみてはいかがでしょうか。
-
-

-
2024年7月:補助金・助成金最新情報
-

補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。
潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。
新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。中小企業省力化投資補助金
中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等に対して、IoT、ロボット等の人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助することにより、簡易で即効性がある省力化投資を促進し、中小企業等の付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的とします。
【補助対象者】
人手不足の状態にある中小企業等【支援内容】
補助対象:補助対象としてカタログに登録された製品等
補助上限額:200万円~1,000万円
補助率:2分の1【実施機関】全国中小企業団体中央会
【詳しくはこちら】
https://shoryokuka.smrj.go.jp/新潟県新事業チャレンジ補助金
エネルギー・原材料価格高騰の影響を踏まえ、中小企業等が経済社会活動の変化に対応するために行う新たな商品開発やサービスの提供の取組であって、地域の課題解決に資するもの、またはDXや脱炭素、省人化・省力化等に関する前向きなチャレンジを支援します。
【補助対象者】
・県内中小企業であること
・一般型については、売上減少要件に該当する事業者であること【支援内容】
重点課題解決型(DX・GX対応枠)
・補助率 3分の2以内
・補助金額上限 133万3千円(補助対象事業費200万円)
・補助金額下限 13万3千円(補助対象事業費20万円)
重点課題解決型(生産性向上枠)
・補助率 2分の1以内
・補助金額上限 100万円(補助対象事業費200万円)
・補助金額下限 10万円(補助対象事業費20万円)【実施機関】新潟県
【詳しくはこちら】
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/challenge202102niigata.htmlDX情報発信支援補助金
市内中小企業者を対象に、販路開拓や人材確保等自社の情報発信のためのホームページ及びPR動画作成の費用の一部を市が負担し、市内中小企業におけるDXを支援します。
【補助対象者】
市内に事務所又は事業所を有する中小企業者【支援内容】
・燕市内のベンダーを利用する場合
対象経費の2分の1(上限20万円)
・燕市内のベンダーを利用しない場合
対象経費の3分の1(上限10万円)【実施機関】燕市
【詳しくはこちら】
https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shien/seido/shienseido/11616.htmlまとめ
新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。
※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。
-
-

-

-
新潟県三条市の企業様のみ:令和6年度 WEBサイト活用支援補助金が発表されました!
-
販路開拓や人材採用が円滑に行えるよう、ホームページ及び企業活動紹介動画の作成を支援し対外的な認知度向上や信頼度の向上につなげることを目的とする補助金です。「WEBサイトの新設・改修」、「企業PR動画の作成」などが補助対象となります。
なお、不明な点などありましたらご相談をお待ちしております。
-
-

-
BtoB向けSNS広告のメリットやおすすめ広告
-

SNSを使っている中でBtoB向けの広告をよく目にするようになってきました。
そんな広告を見て自社でも活用してみたいと興味を持っているものの、実際にどのようにして配信すればいいのか、BtoBで効果はちゃんと出るのか不安だという方は多いのではないでしょうか?
SNS広告といっても様々な媒体があるので、ターゲットとなるユーザー総に合わせた媒体選定やターゲティングが重要になってきます。
今回はBtoB向けSNS広告のメリットやおすすめのSNS媒体などについてご紹介させていただきます。BtoB企業がSNS広告を活用するメリット
そもそも、BtoB企業がSNS広告を活用するメリットとはなんなのか、2つご紹介いたします。
ターゲティング精度の高さ
SNS広告は、業界や役職に応じた精密なターゲティングが可能です。その結果、効率的にターゲットとしている顧客へリーチし、ROIを最大化しやすいメリットがあります。
SNS媒体の多くはMAU(月あたりのアクティブユーザー数)が多いため、その中から様々なKPIに対して自動最適化が可能です。
MAUが少ないリスティング等の媒体よりも、自動最適化の精度が高く、類似ユーザーへのターゲティング等でも、他の媒体と比較して結果につながりやすいです。また、Facebookは実名かつユーザーが登録した年齢や性別エリアに対して、ピンポイントでターゲティングが可能になっております。他媒体では難しい、部署や担当者レベル、またターゲティングしたユーザーに近しいユーザーの細かなターゲティングも可能となっています。
潜在顧客の掘り起こし
時間・場所問わず、仕事やプライベートでもユーザーが日常的にチェックしているSNSに広告を表示することができるため、潜在顧客(まだ商品・サービスは認知していないものの、この先ニーズが顕在化される黄色枠の層)の目に留まり、認知してもらえる効果があります。
広告の露出範囲が広がり、ターゲット層を広げることが可能なため、新たな顧客層の開拓や売上増加を期待できます。また、SNS広告の特徴としてインフィード形式で広告が配信されるケースが多く、各SNSのフィード上に広告を自然に溶け込ませることでユーザーに違和感なく広告を配信させることが可能です。
SNS広告でのターゲティング手法
SNS広告には様々なターゲティング手法があります。
まずはどのようなターゲティング手法があるかを紹介していきます。属性
顧客の属性(年齢、地域、性別、学歴、職業、役職、収入など)によってターゲットを絞り込むことが可能です。
興味関心
興味・関心ターゲティングを設定することで、設定した内容に興味を示しているユーザーへ広告配信ができます。例えば、Meta広告(Facebook・Instagram)でいうと以下のような設定が可能です。
・スポーツ・アウトドア(例:サッカー、ゴルフ、テニス、キャンプ、釣り)
・テクノロジー(例:コンピューター、架電・エレクトロニクス)
・ビジネス・業界(例:不動産、銀行サービス、営業、医療など)
・家族と交友関係(例:デート・恋愛、結婚、子育て、ウェディング)
・買い物・ファッション(例:ショッピング、美容、衣料品)
・興味・アクティビティ(例:ペット、旅行、自動車、食品・飲料品)Webサイトの閲覧履歴
過去Webサイトに来訪したことがあるユーザー、自社のYouTube動画を視聴したことがあるユーザー等に絞って広告を配信する「リターゲティング(リマーケティング)」という手法があります。
リターゲティングを行うメリットとしては「見込み顧客に再アプローチ」できることです。
見込み顧客はコンバージョンに近い顕在層であるため、CVRが高くなり、費用対効果が良くなる傾向にあります。BtoBでおすすめのSNS媒体
Facebook
高精度なターゲティングと配信最適化機能を持つ、Facebookの広告配信プラットフォームへ配信することが可能な媒体です。
また、他のSNSと大きく違う点として、実名制を基本としたSNS媒体のため、正確なデータベースによるターゲティング精度の高さが特徴です。
また、ビジネスパーソンの利用率が高いため、意思決定者にアプローチしやすいFacebook広告はBtoB広告の中でも非常に効果の高い媒体といえます。X(Twitter)
X(Twitter)を通して情報収集やニュースチェックをするユーザーも増えており、幅広いユーザーをターゲットにするには、X(Twitter)広告も有効です。
Xアカウントをターゲットとして指定すると、そのアカウントのフォロワーに似たユーザーへ配信をすることができる「フォロワーターゲティング」が可能なため、意思決定者へのアプローチもしやすくなっています。また、X(Twitter)広告の特徴としてリポスト機能があります。気になるポストがあれば、ユーザーがリポストすることによって拡散され、より潜在層へアプローチできます。
本来狙っていたターゲット以外にも広告が波及し、拡散によりさまざまな層に広告が届く可能性が高まるため、想像しなかった箇所からの反響が見付ける点や、リスティング広告では訴求できない人物に訴求できることが期待できます。Instagram
Instagramは画像・動画のビジュアルコンテンツを通じて製品やサービスを魅力的に紹介できる媒体です。
視覚的なところからブランドイメージを強化し、製品やサービスへの関心を喚起することができます。
「画像」「写真」で印象付けをすることで、「○○といえば▲▲会社」というポジションを獲得できれば、広告によるブランディング効果はより高くなります。まとめ
SNS広告はターゲティングが柔軟にできることが特徴ですので、リスティング広告と比較するとより多くのユーザーに対して配信が可能です。
また、多くのユーザーに対して配信することで、成果を出しつつ潜在層の育成も同時に行うことが可能です。
そのため、ホワイトペーパーなどの資料請求させるようなリード獲得を目的とした広告を実施することで、実績にもつながります。
広告の目的によって配信する媒体を変えることで効果最大化をはかることができますので、ターゲット層やターゲティング内容、予算、クリエイティブなどについて、どうしたらいいのかご不明な際は、ぜひお気軽にご相談ください。
-
-

-
SNSがホームページの代わりにならない理由
-

SNSが普及しているこの時代、SNSだけ運用していてホームページは持っていないという企業・店舗は少なくありません。
確かにSNSは、基本的な利用であれば費用がかからず操作の難易度も高くないことから、運用を始めやすい媒体です。
しかし、SNSはホームページの代わりにはなりません。
今回はSNSがホームページの代わりになれない理由についてご紹介させていただきます。理由は「役割の違い」
理由は様々ありますが、最も大きな理由としてはSNSとホームページそれぞれの「役割の違い」があります。
SNSは基本的に「広く知ってもらう」ための媒体であり、一方でホームページは「深く理解してもらう」ための媒体です。SNSはシェアやいいねなどで認知を取りやすいものになっており、ユーザーは受け身でも様々な情報が入ってきます。
逆にホームページは特定のキーワードでの検索によって認知されるもので、ユーザーが自発的に情報を検索するという行動に移す必要があります。そもそもSNSは短時間でリアルタイムな情報を求めて使っているユーザーがほとんどで、詳しい情報を検索してより深く理解したいと思った際にSNSは不向きです。
SNSは「知ってもらう」という“第一段階”はクリアできるものの、その先の「ブランド・商品・サービスへの理解・共感を得る」という点で効果を十分に発揮しきれずにいる状態なのです。
SNSをホームページの代わりとすることが難しい理由
役割が違くともSNSでも工夫すれば「深く理解してもらう」ことはできるのではないか?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
そこでSNSの特徴を踏まえて、ホームページの代わりとすることが難しい理由を3つご紹介します。情報の一時性
SNSは投稿が即時に流れるため古い情報が埋もれやすく、他コンテンツとの競合も発生します。
ユーザーの行動・心理パターンとして「短時間で素早く情報を取得・消費する」傾向にあるため、ブランド・商品・サービスへの十分な理解を得ることが難しいと言えます。「情報量」「可視性」「デザイン」への制限
SNSでは短文や画像での発信が主流のため、詳細な情報提供が難しい傾向にあります。
また、媒体側のアルゴリズムによって、投稿内容がどの程度表示されるかが左右されてしまいます。
デザインの自由度や掲載内容にも制限があり、媒体側のフォーマットや規定に準ずる必要があるため、なかなか自由にカスタマイズなどすることが難しくなっています。SEO対策の効果が薄い
SNSのコンテンツは検索エンジンに表示されにくく、ホームページほどSEO対策の効果が期待できません。
SNSとホームページの最適な使い分け
SNSの活用(知ってもらう)
SNSはブランドの認知度アップやコミュニケーションを重視する場合に効果的です。
リアルタイムな情報発信やユーザーとの対話を通じて認知度を高め、フォロワーとの関係を構築します。ホームページの活用(深く理解してもらう)
ホームページは詳細な情報提供やブランド理解を深めるケースに適しています。
企業のビジョンや商品・サービス、企業情報などを掲載し、訪問者にブランド価値の理解・共感をしてもらうことができます。まとめ
SNSとホームページは「相互補完」の関係にあります。
SNSでブランドの認知度を高めた後、ホームページへ誘導して詳しい情報を提供することでユーザーのブランド理解をより深めることができます。
逆に、ホームページからSNSへのリンクや埋め込みを設置し、フォロワーとの関係を強化することも重要です。
SNS、ホームページどちらか片方だけではなく、両方を上手く活用していきましょう。
アイサポートではどのように活用したらよいかなどの相談も受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
-
-

-
【DX宣言】デジタル変革で未来を切り拓く
-

近年、企業における「DX(デジタルトランスフォーメーション)」への注目度が急速に高まっています。
DXとは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスの変革を図る取り組みを指します。従来の業務を効率化したり、顧客体験を向上させたりするだけでなく、新たな事業機会の創出や、競争力強化にもつながるため、多くの企業がDX宣言を発表し、積極的に取り組んでいます。
DX宣言とは?
DX宣言とは、企業がDXを推進する決意表明を表明するものです。宣言の内容には、経営理念に基づいたDXのビジョンや目標、具体的な推進計画などが盛り込まれています。
DX宣言は、社内外にDXへのコミットメントを伝えることで、関係者の一体感を生み出し、推進を加速させる効果があります。DX宣言の内容
DX宣言には、以下の要素が含まれることが一般的です。
経営理念に基づいたDXのビジョン、目標
なぜDXに取り組むのか、どのような未来を実現したいのかを明確にする。
具体的な推進計画
DX推進のための組織体制を構築する。
DX推進リーダーを任命し、責任と権限を明確にする。人材育成
DXに必要なスキルや知識を備えた人材を育成する。
社員全体への研修を実施する。評価制度
DX推進における成果を評価する制度を導入する。
インセンティブ制度などを活用して、社員のモチベーションを高める。DX宣言の事例
多くの企業がDX宣言を発表し、積極的に取り組んでいます。いくつか事例をご紹介します。
株式会社NTTデータ
2020年5月に「NTT DATA DX宣言」を発表。
「顧客中心のデジタル企業へ」というビジョンを掲げ、AI、IoT、ビッグデータなどの先端技術を活用したDXを推進している。富士フイルム株式会社
2021年3月に「富士フイルム DX宣言」を発表。
「ヘルスケア、グラフィックシステム、マテリアルズの3つの事業領域におけるDXを推進し、社会課題の解決に貢献する」というビジョンを掲げている。ソフトバンクグループ
2018年9月に「SoftBank Group DX宣言」を発表。
「AI、IoT、5Gなどの先端技術を活用したDXを推進し、グループ全体の競争力強化を図る」というビジョンを掲げている。まとめ
DXは、企業が生き残るために必須の取り組みです。DX宣言は、DXへのコミットメントを表明し、推進を加速させる効果があります。
まだDX宣言を発表していない企業は、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
今後の長期的な計画やどのようなことが必要なのか、わからないことがあればぜひご相談ください。
-
-

-
問い合わせ対応を効率化!問い合わせ管理について
-

かつてメールが主流だった顧客からの問い合わせは、近年問い合わせフォームやSNS、チャットなど問い合わせの手段が色々と増えてきています。
問い合わせ管理システムとは、問い合わせ内容や顧客情報を管理できるツールです。メールや電話・SNS・Webサイトからの問い合わせをまとめて管理でき、カスタマーサービスを効率化することができます。
今回は問い合わせ対応を効率化・自動化したい方に向けて、問い合わせ管理システムの概要やメリットなどについてご紹介させていただきます。問い合わせ管理システムとは?
問い合わせ管理システムとは、顧客やユーザーからの問い合わせを一元管理するシステムを指します。
メールや問い合わせフォーム、SNS、チャットなど様々な手段を通じてくる顧客からの問い合わせを一元管理しなければ、一貫した適切な対応は難しくなります。また複数のチャネルを使い分けるのは手間と時間を要します。
そのようなときに問い合わせシステムを導入すれば、情報を一元管理し、業務効率化を図れるようになります。問い合わせ管理システムを導入すると、以下のように業務を効率化できるようになります。
・複数プラットフォームからの問い合わせを1箇所に集約
・問い合わせの対応状況をステータス管理で視覚化
・対応漏れや二重対応の防止
・担当者割り当ての自動化
・FAQやテンプレートの活用による対応時間の短縮問い合わせ管理システムのメリット
問い合わせの一元管理による業務の効率化
問い合わせ管理システムを導入すると、顧客の問い合わせ対応をおこなっているメーラーやSNS、チャット、各ECサイトなどに都度ログインする必要がなくなり、一元管理を実現できます。
担当者を自動で割り当てることでだれが対応するかを確認せず済み、対応がどこまで進んでいるかのチェックも容易です。過去の対応状況も、ひとつの管理画面から検索できるので効率的です。対応状況をリアルタイムに共有
問い合わせ管理システムでは、従業員が行っている問い合わせ状況の進捗をリアルタイムで確認することができます。
それにより、フォローが必要であれば適切なタイミングで行えるようになります。さらに「誰が・どの顧客に対応しているのか」がわかるため、二重対応を防げます。従業員の対応負担の軽減
テンプレート機能やFAQ、ナレッジベースなどを活用すれば、問い合わせのたびに新たに一からメールを書き起こしたり、必要な資料を探したりしなくてよくなります。
オペレーターが対応にかける時間を短縮できるのも、問い合わせ管理システムのメリットです。顧客情報の表示・ステータス管理
顧客の属性や対応状況を管理できるのも問い合わせ管理システムのメリットです。
例えば「顧客の問い合わせ回数」や「過去の問い合わせ内容」などを把握しやすいため、過去の状況を参考にしながら適切な対応ができるでしょう。
さらに「未対応、保留中、対応中、完了」など、現在問い合わせのどの段階なのかがわかるのも特徴です。問い合わせ管理システムの上手な活用の仕方
振り分けとステータスのルール設定
各プラットフォームから届いた問い合わせは、フォルダで振り分けるルールを設定すると管理が容易になります。たとえば以下のように「流入元>内容>対応内容」でファネル管理すると、内容を把握しアクションを起こしやすくなるでしょう。
<例>
「ECサイト」「代表メールアドレス」>「問い合わせ」「苦情」>「返品」「交換」「見積もり」などさらに「未対応」「対応中」「対応済」など一目で対応状況がわかるようステータス設定できるようにしておくと、対応漏れや二重対応を防げます。
問い合わせフォームの改善
問い合わせ管理システムに届くメールなどが、フォルダに適切に振り分けられるよう、問い合わせフォームの改善もあわせておこないましょう。
たとえばタイトルにプラットフォームの名前が入るようにすれば、問い合わせ管理システムに届いた時点で自動にフォルダへ振り分けが可能です。テンプレートやFAQの整備
これまでの問い合わせと対応内容を整理し、ひな形となるテンプレートやFAQ、ナレッジベースを整備するのも業務の効率化には欠かせません。テンプレートやFAQは、オペレーターの対応スピードの向上や、対応品質の均一化に貢献するためにも都度整備していくことが重要です。
問い合わせ管理システムに備わっている機能を活用し、整備を進めていきましょう。まとめ
問い合わせ管理システムを導入すると、複数チャネルからの問い合わせを一元管理できるため、業務効率化を図れます。
また、対応状況をリアルタイムに確認・共有できたり、従業員の負担を減らしたりできるメリットがあります。
問い合わせ管理システムを導入する際には、事前に目的や必要な機能を洗い出し、費用対効果も考慮して選ぶことが大切です。
問い合わせ管理システムを有効活用して、顧客管理や対応を効率化しましょう。
-
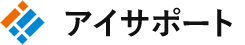
![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)