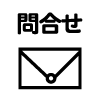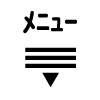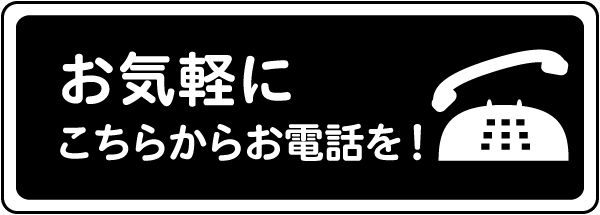新着情報
-

-
いまさら聞けないSSL化について
-

ウェブサイトの運用や管理をしているとよく聞く単語「SSL(えすえすえる)化」。
実はこのSSL化はウェブサイトを用いる上で現在必須といっていいほど重要なものになっています。
今回はそんなウェブサイトを管理・運用しておくならば知っておきたいSSL化についてご紹介させていただきます。SSL化とは
SSL(Secure Sockets Layer)とは、サイトを閲覧するユーザーとの通信のやり取りを暗号化する仕組みです。
この技術はネット上のさまざまな場面で使われており、たとえば「ショッピングカート」や「お問い合わせフォーム」といった個人情報が入力される場面でよく使われます。そんな「悪意のあるユーザーから情報の安全を守る」仕組みであるSSLですが、この通信を用いているか否かはウェブサイトのURLを見れば一目瞭然です。

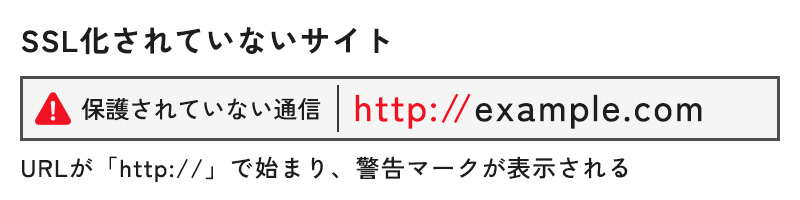
SSLの2つの役割
SSLには大きな役割があります。
それは『インターネット回線を介してやりとりされる情報を暗号化する』というものです。
ちなみに、SSLにはその役割以外にももうひとつ『Webサイトの「所有者」が誰かを証明する』という大きな役割があります。やりとりされる情報(データ)の「暗号化」
ショッピングサイトを利用する際に、クレジットカード決済を利用して商品などを購入する場合があると思います。
もし、利用しているショッピングサイトがSSL化されていない場合、入力したクレジットカード情報は「誰でも読める状態」のまま、サーバーに届きます。
そうなると、第三者によってクレジットカード情報が盗み見される恐れがあります。SSL化されていれば、サーバーに送られるクレジットカード情報などの個人情報は暗号化された形で送信されるので、第三者に盗み見られることが無くなります。
サイト所有者の証明
サイト所有者の証明とは、「このサイトの所有者は信頼できるよ!」ということを、「CA(Certification Authority)」と呼ばれる認証局に証明してもらうことを指します。
SSLを導入すると、「電子証明書」と呼ばれるものが認証局から発行されます。
この電子証明書は、「そのサイトが信頼できるかどうか?」という証明書としての役割のほかに、暗号化されたデータを復号化するためのカギとしての役割もあります。SSL化されているということは、きちんとドメインの管理者が導入の設定を行い、証明書を発行されることで「このドメインは信頼できますよ!」ということを証明してくれています。
SSL化のメリット
検索エンジンで表示されやすくなる
2014年にGoogleが常時SSL化されているかどうかというのを検索順位を決定する要素の1つと発表しました。
GoogleがウェブサイトのSSL化の有無を検索順位に組み込むようになってからはSSL化の有無がSEOにおいても重要な項目となっています。
SSL化をしただけで検索順位が大きく変化するというわけではありませんが、SSL化をしていないサイトに比較すると上位に表示されやすくなります。正確なアクセス解析が可能になる
Googleアナリティクスでリファラー(参照元)が正確に解析可能になります。
https://(SSL化対応)ページからhttp://(SSL化非対応)ページへの流入は情報が暗号化されていない影響によりdirectと表示されます。
directはブックマークやURLを直接入力したものという印象が強いのですが、こういった解析へのデメリットが生じるきっかけとなります。
https://ページからhttps://ページへの流入は、どのドメイン由来なのかという確認ができます。セキュリティによるユーザーの信頼
情報のやり取りが暗号化されているので個人情報を含むアクセス情報の盗聴・改ざんの心配がありません。
また、警告マークや警告メッセージによる不信感からユーザーがページを離脱する、という事を防ぐことが可能になります。まとめ
SSL化はこれからのWEBマーケテイングには既に欠かせない要素となっています。
ユーザーが安心して使用できるサイトを作ることは企業の責任の一つであり、そうすることは自ずと自社の利益へ繋がります。
デジタル化がどんどん進んでいく中で、ウェブサイトのセキュリティにも力を入れてユーザーが安心して閲覧できるサイトを構築していきましょう。
-
-

-
LINE公式アカウントを使った販促・集客方法について
-

先週、LINE公式アカウントで配信するメリットについてご紹介させていただきました。
今回は実際にLINEを活用した際にどのようにして販促・集客につなげればいいのか、具体的な方法も含めご紹介させていただきます。販促・集客に「LINE」が効果的な理由
昨今、販促や集客に活用されているSNSが多数ある中で、LINEを使っている企業が増えてきています。
その理由は、LINEはいまや日常生活に欠かせないコミュニケーションツールとなっているからです。
LINEの国内月間利用者数は、日本人口の約76%にあたる約9500万人(2023年3月末時点)。
ユーザーの8割以上が毎日利用しており、年代は10代から60歳以上までさまざまです。しかも、普段利用しているSNSはLINEのみというユーザーも数多く存在しています。さらに、LINEには以下の特徴があります。
・配信されたメッセージがポップアップで表示されるので気づかれやすい
・他のメッセージを確認するためにトーク画面を開いたついでに、メッセージを開封してもらえる
・メールのように迷惑フォルダに振り分けられず、送ったメッセージが必ず届くこれらの特徴により、送ったメッセージの開封率の高さもLINEが選ばれる決め手となっています。
開設後、「友だち追加」してもらう方法
販促・集客でLINEを活用するには、まずは「LINE公式アカウント」を開設し、多くのユーザーに「友だち追加」してもらうことが重要です。
LINE公式アカウントの開設で利用できる基本機能を活用する
①お礼に「クーポン」をプレゼントする
LINEではデジタルクーポンを発行できるので、友だち追加のインセンティブとして利用しましょう。
その後も定期的に「友だち限定」として配布すれば、お得感を感じた他のユーザーが情報拡散し、新たな友だちを得られる可能性があります。②初回ボーナス付きの「ショップカード」を発行する
LINE公式アカウントでショップカードを発行するには友だち追加が必要なので、自然な流れでユーザーに友だち追加を促すことができます。また、通常時よりも付与ポイント数が高い、初回ボーナス付きで設定することも可能です。LINE公式アカウント管理画面を活用する
①SNSでLINE公式アカウントを宣伝する
「友だち追加ガイド」内の「URLを作成」で友だち追加用のURLを作成し、SNSやメールにてシェアしましょう。②Webサイトに「友だち追加」ボタンを設置する
「友だち追加ガイド」内にて「友だち追加ボタン」を作成し、ホームページやブログ、メールマガジンなどに貼り付けてアピールしましょう。
サイト内の目立つ場所に設置すると友だち追加してもらえる可能性が高くなります。③店頭POPを活用する
実店舗がある場合は、レジ横などに友だち追加を促す店頭POPを飾りましょう。LINE公式アカウントを運営する上での注意点
友だち追加してもらったユーザーと末永く良好な関係を維持するためにも、「ブロック」や「友だち解除」されないよう配慮が必要です。
適切な配信頻度とタイミングに注意する
メッセージを配信する際、配信頻度とタイミングによっては、ユーザーに「鬱陶しい」と思われブロック・友だち解除される場合があります。
業種によって適切な配信頻度は異なりますが、まずは週1回を目安に配信するのが妥当です。
タイミングについては、通勤・通学のすきま時間、仕事や家事が一段落ついた19時以降など、ターゲットとするユーザーの生活リズムに合わせることをおすすめします。喜ばれるような配信を定期的に行う
新商品やセールの案内、限定クーポンの配布など、ユーザーのメリットになる配信を定期的に行うことで、ユーザー離れを回避することができます。
また、ユーザーのメリットになる内容は、配信頻度が高くても受け入れてもらいやすい傾向があります。まとめ
LINE公式アカウントを活用し、販促・集客を行うには、まずは多くの友だちを獲得することが重要です。
その際にもっとも効果的なのが、友だち追加してもらった「お礼」の付与です。
また、友だち追加後も定期的にユーザーに喜ばれるような配信を定期的に続けることで、「ブロック」や「友だち解除」されないようにすることも大事になってきます。当社ではLINE公式アカウントの開設だけでなく、その後も配信についても請け負っております。
気になった方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。
-
-

-
LINE公式アカウントで配信するメリット
-

最近、企業や店舗を運営している方のみならず、個人でもLINE公式アカウントを運用したいと考えている方も増えてきています。
LINE公式アカウントの開設を検討しているけど、そもそもどんなことができるのか把握していない…となっている人もいるかと思います。
今回はLINE公式アカウントを活用するメリットについてご紹介していきます。
まだLINE公式アカウントを活用していない方や、これから活用したいという方は、導入するかどうかを判断するために是非ご確認ください。LINE公式アカウントについて
「LINE公式アカウント」は、日本国内で月間9,600万人(2023年12月末時点)が利用するコミュニケーションアプリ「LINE」上で、友だち追加してくれたユーザーに直接情報を届けることができるサービスです。
日本の人口の約70%、9,600万人という多くのユーザー数を誇るLINE上にアカウントを作成することで、販促や集客に関するさまざまな施策を実施することができます。LINEで配信するメリット
LINEでさまざまな情報をお客様に向けて配信することには、次のようなメリットがあります。
・メルマガよりも開封されやすい
・LINEを利用しているユーザー数が多く、年齢層が幅広い
・友だち登録が簡単
・リアルタイムで情報を発信できる
・自動返信やステップ配信で自動化できる
・1対1でユーザーとチャットできる
・集客やマーケティングに最適LINEはアプリでメッセージを配信するため、メルマガ配信でよくある利用していないアドレスでの登録や迷惑メールへの振り分け、配信したメールの不達などがありません。
ユーザー側からブロックされない限り、定期的にお知らせしたい情報をメッセージにして届けることができます。
さらにLINE公式アカウントの配信は、メールよりも開封率が高いといわれています。
メッセージの到達率はもちろん、配信内容の気付きやすさ、開封率、クリック率などメルマガで配信するよりも効果が高くなっています。
したがって、従来のメルマガ配信よりも、LINE公式アカウントでの情報発信の方が効果的なマーケティングが行えることでしょう。また、LINE公式アカウントでは、一斉送信や自動応答メッセージ、ステップ配信などのさまざまな機能を利用することができます。
これらを活用することでメッセージの対応を効率化・自動化することができます。LINE配信での注意点
LINE公式アカウントは無料でメッセージを配信できますが、月200通以上配信するとなった場合は有料プランとなります。
月5,000円で5,000通まで配信できるようになります。
しかし、郵送や新聞、フリーペーパーなどを利用して新商品や季節の商品などを紹介している場合と比較しますと、最大5,000人に5,000円でタイムラグ無しに配信できるのはメリットと言えることでしょう。まとめ
今回はLINE公式アカウントで配信するメリットや注意点について、ご紹介いたしました。
LINE公式アカウントを開設し、運用していけば集客や業務効率化に役に立つことでしょう。
当社でもLINEを使った販促サポートを行っております。
LINE公式アカウント開設のご相談や運用についてのご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
-
-

-
第三者による期限切れドメインの悪用を防ぐには
-

インターネットが年齢層を問わず幅広く利用されるようになった現代において、企業や自治体が広報のためにWebサイトを立ち上げる事例が多くあります。
ここで問題になるのが、一時的に利用したドメインの期限切れによる、他者による悪用の被害です。企業におけるドメインの利用
ドメインとは、インターネットにおいてWebサイトを提供しているコンピュータの住所を指し示す情報になります。
新しいドメインを使いたい企業は、希望する名前で申請し、利用料を支払います。企業においては、一度企業名などのドメインを取得した後は、用途に応じて「サブドメイン」を利用するケースが多いです。例えば「○○○.com」というドメイン名を所持している企業であれば、「×××.○○○.com」や「△△△.○○○.com」の「×××」「△△△」の部分がサブドメインとなります。
主となる独自ドメインを取得すれば、サブドメインは自由に作成することができるため、顧客向けのショッピングサイトや会員向けサイト、期間限定サイトではサブドメインでURLを分けることが一般的です。
期限切れドメインが悪用される?
ドメイン名は期限があり、通常は年単位で利用期間を更新します。
利用しなくなれば、更新手続きを行わずに手放すことがあります。手放されたドメインは一定期間は利用停止状態になり、元の所有者が復元できます。
他者はその期間中に同じドメインを取得することはできません。一定期間が経過すると、他の利用者がそのドメインを利用できるようになります。この制度を悪用した事例が報告されています。長野市にある地元企業の公式ウェブサイトのURLで、市とは無関係な内容が発信されていました。
実施したキャンペーンの期間が終了し、手放したサイトのドメインを第三者が取得していたようです。
公的なサイトは検索サービスからアクセスを得やすいため、全国の自治体で流用される事例が相次いでいます。ドメイン悪用を防ぐには
企業においてドメインを利用するときに、どのようなことに気を付ければ良いのでしょうか。
ドメインの利用期間を把握する
ドメインには登録期限があり、1年単位で最大10年まで申請が可能です。
期限が近づくと、更新手続きをすることで同じドメインを継続利用できます。しかし、更新を忘れると45日間の「自動更新猶予期間」後に他者が再登録できる状態になります。企業や組織のドメインの乗っ取りは、この更新手続きをしなかったことにより発生することがあります。登録期限内でも他者に移管できる場合があり、移管依頼を受けた場合、10日以内に返事がこなければ自動的に承諾されます。
この仕組みを悪用して乗っ取りが起こることがあり、対策としては定期的な更新手続きや利用停止後のプロセスを事前に決めることが重要です。また、利用規約を確認し、移管手続きの流れを把握することで、乗っ取りを未然に防ぐことが可能です。
サブドメインの活用
企業が新商品やイベントに合わせてドメインを使用する際、新しくドメインを取得するのではなく、サブドメインを活用するのもよいでしょう。
例えば、「新商品.example.jp」のような形です。これにより、不必要なドメインの取得や管理の手間が軽減されます。
多くのドメインを持つと利用期間や類似ドメインの管理が複雑になり、企業とドメインの結びつきがわかりにくくなり、なりすましサイトのリスクも増えてしまいます。サブドメインは元のドメインの利用が許可されていれば、基本的に自由に追加できます。サブドメインを活用することで、企業は広報やサービス提供に役立てることができます。
まとめ
ブランドイメージの損害を避けるために、ドメインの管理プロセスを見直し、適切に運用していくことが大切です。
-
-

-
企業ブログはどう書けばいいの?書き方のポイント教えます。
-

多くの企業が自社のホームページを運営し、その中で一つの有力な情報発信手段として「ブログ」を活用しています。
しかし、初めて自社ブログを書こうとすると、「どう書けばいいのか?」や「どんな内容にすればいいのか?」といった疑問が湧いてきますよね。今回は、自社ブログの書き方やネタの出し方について紹介します。企業ブログの基本的な書き方
企業ブログを書く際の構成とポイントをまとめてみました。
以下の基本的な構成を意識してまずは書いてみましょう。1. ブログタイトル
ブログの肝となる部分。タイトルは簡潔で分かりやすく、読者の注意を引く工夫が必要です。
例えば、「〇〇のやり方」、「○○の理由とは?」など2. アイキャッチ画像(トップ画像)
視覚的な要素が読者を引き込みます。タイトルと連携し、記事の雰囲気を伝える適切な画像を選びましょう。3. 冒頭部分
記事の核心を端的に伝え、読者の関心を引きます。冒頭で「なぜこの記事を読むべきなのか」を伝えることが重要です。4. 本文
詳細な内容や情報を提供する部分です。段落に区切り、箇条書きや見出しを活用して読みやすく構成します。5. まとめ部分
記事のまとめや結論を簡潔にまとめます。読者に記事を振り返らせ、印象に残るようなまとめ文を心がけましょう。初めてのブログでは、「結論→理由」の流れで書くとよいでしょう。まず、結論を明確にし、その後に詳細な理由や根拠を述べることで、読者はスムーズに理解しやすくなります。
企業ブログネタの出し方について
ブログを始める際、ネタが尽きるのではないかと心配になることもあるでしょう。
しかし、ネタ探しは意外なビジネスチャンスに繋がることもあります。そんな方に向けて、ブログのネタ探しのヒントとなるアイデアをご紹介します。関連キーワードを検索してみる
自社のサービスや事業に関連したブログを執筆する際には、Google検索や関連キーワード検索が役立ちます。
具体的なキーワードを基にして検索数が多いものを見つけ、それに基づいてネタを出すことが重要です。
例えば、「サプリメント 飲み合わせ」などのキーワードでの検索数が多ければ、サプリの飲み合わせに関する情報が求められていることが分かります。人に聞いてみる
社内メンバーや取引先の方々に対して、日常的な世間話の中で、有益なブログネタを見つけることができます。
「最近、お客様と話していて印象的だったことは?」や「弊社の商品について知りたいことはありますか?」などの質問を通じて、ネタのヒントが生まれることがあります。Q&Aサイトをチェックしてみる
「Yahoo知恵袋」や「教えて!Goo」などの質問サイトを活用して、自社のサービスや商品に関連したキーワードを検索することで、顧客が抱える疑問や求めている情報を直接知ることができます。これをネタにしてブログを書くと、顧客にとって有益で価値のあるコンテンツを提供することができます。
まとめ
企業ブログは、いずれは会社発信のメディアとして大きな存在感を持つことになります。
自社のファンを育成し、高いマーケティング効果を生み出す可能性があります。
定期的に更新し、ぜひ自社ブログを価値のあるコンテンツにしていきましょう。
-
-

-
業界外の人でも分かる!レスポンシブWebデザインとは
-

Web制作会社のホームページで頻繁に出てくる言葉に「レスポンシブ」というものがあります。
レスポンシブとは「レスポンシブWEBデザイン」の略語であり、PCやスマートフォンなどの画面サイズが異なるデバイスに、ホームページを柔軟に対応させる制作手法(構築手法)のことです。
今回は、Webサイトを制作する上で必ずと言っていいほど出てくる「レスポンシブ」について改めてご紹介したいと思います。レスポンシブWebデザインとは
Webサイトを制作する際、できればコストをかけてPCとスマホを別々のデザインで制作するのが、サイト利用者にとってとても見やすいサイトになります。ただこれではWebサイトの制作者にとって、Webサイト更新時のコストが2倍になり、運用を継続するのは難しくなりがちです。
そういった場合に、レスポンシブの考え方が役立ちます。
PCなのかスマホなのか、Webサイトを利用する機器によってディスプレイの大きさが変わるため、どんな画面サイズでもわかりやすい画面表示が必要です。このように効率的に「切り替え」をする考え方や具体時な手法を、レスポンシブWebデザインといいます。画面幅が、378px以下はスマートフォン、1,024px以上はPC、その間の379px〜1,023pxがタブレットといったように判断をし、WEBサイトをそれぞれで綺麗に表示できるよう制作するのがレスポンシブWEBデザインです。
レスポンシブWebデザインのメリット
レスポンシブWebデザインを実装する大きなメリットには、以下の3つがあります。
ユーザーの利便性が向上する
レスポンシブWebデザインは、ユーザーの利便性が大幅に向上します。
例えば、パソコン版のページレイアウトにしか対応していない場合、スマートフォン版から該当のWebサイトにアクセスをすると文字が小さくて読めない、画像が大き過ぎて切れるなどの不具合が起こりやすいです。
ユーザーは見にくいWebサイトを見ようとは思わないため、途中で離脱してしまったりそもそも閲覧するのをやめるようになったりする可能性があります。
レスポンシブWebデザインを採用すれば、どのデバイスからWebサイトとアクセスをしても見やすく表示でき、ユーザーがストレスなく使える環境が構築できます。Googleに評価されやすい
レスポンシブWebデザインは1つのURLにパソコン版やスマートフォン版、タブレット版をまとめられるため、重複コンテンツが無くなり、Googleのクロールや評価を下げてしまうなんてことが無くなりました。
また、Googleはモバイルフレンドリーを推奨しています。
Googleはスマートフォンが普及した現在において、どのようなデバイスからでも見やすくユーザーの利便性を確保できるWebサイトが重要だと考えています。
今後はGoogleの評価の基準がスマートフォンサイトの内容となるため、レスポンシブWebデザインに対応していないとGoogleから正確な評価を受けられなくなる可能性があります。
逆に言えば、きちんとレスポンシブWebデザインでWebサイトを構築し、スマートフォンで見た際にも見やすいデザインにすれば、Googleから正確に評価されるようになるため、SEO対策としても有効です。Webサイトの管理がしやすくなる
レスポンシブWebデザインは、長期的なコンテンツの管理、運営がしやすいところもメリットの1つです。
レスポンシブWebデザインはコンテンツの内容を記述するHTMLファイルが1つで済むため、コンテンツの追加や修正、更新を行う際には1つのファイルを修正するので、手間がかかりません。
仮にパソコン版とスマートフォン版、モバイル版でURLを分けて運営していたとすると、それぞれにHTMLファイルが存在するので、3つ分のコンテンツの追加や更新、修正が必要となり、時間と手間がかかります。長期的にWebサイトの運営をするには、日々の業務を少しでも減らし負担感なく継続することが欠かせません。
レスポンシブWebデザインを導入すると、コンテンツの管理がしやすくなります。レスポンシブWebデザインの種類
レスポンシブWebデザインには、主に下記の4つの種類があります。
レスポンシブレイアウト:画面の幅の数値に合わせてCSSの切り替えを行うレイアウト
リキッドレイアウト:数値を指定せず、デバイスの画面幅に応じて柔軟にレイアウトを変更させる手法
フレキシブルレイアウト:リキッドレイアウトにプラスし画面の最小幅と最大幅を指定できる手法
グリッドレイアウト:画面の幅に合わせてボックス型のコンテンツを並べる手法まとめ
レスポンシブWEBデザインは比較的近年に開発された構築手法であり、一昔前は各デバイスごとにホームページを制作していました。
しかし、現在はレスポンシブWEBデザインという構築手法が登場したことで、まず一つのパターンを作り、それにプログラミングコードを書き加えることで他のデバイスにも対応させることができるようになりました。
パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットが普及した現在は、レスポンシブWebデザインが欠かせません。
ユーザーが使いやすく見やすいサイトを制作し、利便性を上げることでアクセス数アップにも繋がりますので、まだレスポンシブWebデザインにしていないサイトがありましたら、ぜひレスポンシブ対応を視野に入れてみてください。
-
-

-
日本語対応を開始した対話型AI「Bard」について
-

Bardは、Googleが開発した会話型のAIサービスです。
Googleが開発してきた「LaMDA」と呼ばれる大規模言語モデル (LLM) をベースにつくられ、2022年にリリース、2024年2月現在は試験運用中として公開されています。
Bardはリリース時点では英語のみで使用可能でしたが、2023年5月に日本語対応を開始し、話題になっています。
BardもChatGPTと同様に、幅広い質問に対して、人間のようなテキストで回答できる対話型のサービスです。
今回は、そんな対話型AI「Bard」についてご紹介したいと思います。Bardの特徴
Bard の主な特徴は次のとおりです。
大規模な言語モデル
大量のテキストデータでトレーニングされているので、幅広いプロンプトや質問に応じて人間のようなテキストを生成できます。
たとえば、文章の要約や何らかのトピックに沿ったストーリーを作成する、などといったことができます。広範囲な知識、オープンエンドな回答
「日本の首都は?」というような簡単な質問だけでなく、「日本の首都が東京になった理由は何ですか?」というようなオープンエンドクエスチョンかつ高度な説明が必要な質問に答えることができます。
創造的
メール、手紙、楽曲、詩、コードなど、さまざまなクリエイティブなテキストコンテンツを生成できます。
例えば、「日本の春をテーマにしたポエムをつくって」とお願いすれば、ゼロからポエムを生成してくれます。BardとChatGPTとの違い
BardとChatGPTはどちらも会話型のAIサービスであり、テキストの生成、言語の翻訳、さまざまな種類のクリエイティブコンテンツの作成、質問への回答を行うことができます。
ただし、この2つにはいくつかの重要な違いがあります。サービス価格
Bardは2024年2月現在試験運用中ですが、全ての機能を無料で利用できます。
ChatGPTでは、無料版と月額20ドル支払うことで利用できる有料版があります。有料版では新しいLLM「GPT-4」が利用でき、より精度の向上したサービスを利用できます。回答内容・回答精度
BardはGoogle検索の情報を取り込んでいると言われており、最新の情報に対応した精度の高い回答が得られることが多いです。
一方、ChatGPTは、“会話”に重点を置いているため、会話の流れをより自然に維持し、ユーザーの質問に応じて、よりパーソナライズされた回答を提供できます。ただし、2021年9月までの情報を基に学習しているため、最新ではない情報に基づく回答になる場合があります。連携サービス
OpenAIが開発したChatGPTは、Microsoftが出資していることもあり、Microsoftのサービスに組み込まれやすい傾向があります。
一方で、BardはGoogleが運営しているため、Gmail やGoogleドキュメントと早くも連携されています。Bardの活用方法
Bardの主な活用方法をBardに提案してもらいました。
【質問への回答】
・単純な事実の質問や、複雑なオープンエンドの質問への回答
・質問に対する多角的な視点からの回答【テキスト処理】
・テキストの翻訳
・テキストの要約【クリエイティブなコンテンツ生成】
・詩、楽曲、ストーリーの作成
・コード、スクリプトの記述
・メールや手紙の作成【教育面でのコンテンツ生成】
・エッセイ、プレゼンテーション、レポートの作成
・テスト、クイズ、アンケートの作成【その他のコンテンツ生成】
・チャットボットの作成
・仮想アシスタントの作成まとめ
今回はGoogleが開発するBardについて紹介しました。
対話型AIサービスは、ChatGPT(Open AI社、Microsoftが出資)、GoogleBardの他にも、Amazonが参入しています。さらに対話型以外にも生成AIという点で、画像生成AIのStable Diffusion、動画生成AIのMake A Video(Meta社)など様々なAI・サービスが広がりを見せています。
今後も様々なAIツールが登場してくると思いますので、引き続き気になるツールを見つけたらブログ、もしくはニュースレターなどでご紹介させていただきます。
-
-

-
2024年2月:補助金・助成金最新情報
-

補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。
潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。
新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
【補助対象者】
・小規模事業者であること
・資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
・確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと 等【支援内容】
上限額:[通常枠]50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
補助率:3分の2以内(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は4分の3)【実施機関】全国商工会連合会
【詳しくはこちら】
https://r3.jizokukahojokin.info/ものづくり補助金
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
【補助対象者】
以下のいずれかの要件を満たすものに限ります。
・中小企業者(組合関連以外)
・中小企業者(組合・法人関連)
・特定事業者の一部
・特定非営利活動法人
・社会福祉法人【支援内容】
各申請枠によって変動【実施機関】中小企業庁及び独立行政法人中小企業基盤整備機構
【詳しくはこちら】
https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.htmlまとめ
新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。
※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。
-
-

-
GDPRとは?日本での影響や概要について
-

近年個人情報の取り扱いに関するニュースをよく見るようになってきました。
日本でも個人情報保護法が改定されましたが、まだWeb上のデータに関しては大きく問題視はされておりません。
一方海外では、数年前からWeb上の個人を特定する情報(IPアドレスやCookieなど)に関しても問題視され始めました。そのような流れを受け、GDPRという法律が施行されています。
今回は、GDPRとは何か、またその影響などに関してご紹介していきたいと思います。GDPRとはなにか?
欧州議会、欧州理事会および欧州委員会が策定した新しい個人情報保護の枠組みです。
「EU一般データ保護規則」(GDPR:General Data Protection Regulation)が正式名称となります。
企業による個人データの取得利用を規制する目的で、欧州会議で2016年に可決され、2年間の猶予期間をもって施行されました。GDPRにおける個人情報の処理について
GDPRでは個人データは「識別された、または識別され得る自然人に関するすべての情報」と定義されています。
下記が具体的な定義されている個人データです。
●氏名
●識別番号
●住所
●メールアドレス
●オンライン識別子(IPアドレス、クッキー)
●クレジットカード情報
●パスポート情報
●身体的、生理学的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的、社会的固有性に関する要因GDPRの罰則について
GDPRに従わなかった場合、最大で企業の全世界年間売上高の4%以下、もしくは2000万ユーロ以下のいずれか高い方が適用されます。
現在(12月22日時点)1ユーロが156.47円ですから、円換算すると2000万ユーロは約31億円にもなってしまいます。
最低でも31億円を支払わなければならないというのは、企業にとって非常に大きな損害です。GDPRの日本への影響は?
従わなければ多額の罰金が課せられてしまうGDPRですが、実はEU諸国にのみ適応される訳ではありません。日本でもGDPRを遵守しなければならない場合があります。
GDPRの対象企業
対象となるのは以下の企業です。
・ EUに子会社や支店、営業所などを有している企業
・ 日本からEUに商品やサービスを提供している企業
・ EUから個人データの処理について委託を受けている企業EU圏内にいるユーザーのWeb上の行動データを取得している場合もGDPRの範囲に含まれています。また、以下の条件も対象となるのでご注意ください。
・短期出張や短期旅行でEEA内に所在する日本人の個人データを日本に移転する場合
・日本企業から EEA内に出向した従業員の情報(元は日本から EEA内に移転した情報)
・日本から EEA内に個人データを送付する場合(基準に沿って EEA内において処理されなければならない)
・日本から EEA内に個人データが送付され、EEA内で処理された個人データを日本へ移転する場合GDPRの対応方法
現時点では日本向けの日本語対応のみの商品、サービスであれば特別な対応をする必要はないようです。
しかし、上述したようにEU圏にいるユーザーが使用している可能性もありますので、もしCookieなどの情報を取得しているのであれば、EU圏内からのアクセスがないか、調べてみた方がいいかもしれません。また万が一多くのアクセスがある場合や、EU圏内のユーザーに向けた商品、サービスを展開している場合は上述したようにGDPRの個人情報の処理を遵守するようにしてください。
まとめ
GDPRは既に施行が始まっています。
GDPR違反による制裁事例はまだ確認されていませんが、サイバー攻撃やセキュリティ不備による顧客情報流出事故はGDPR施行後も継続的に発生しており、当該事故がGDPRの制裁対象となっても不思議ではありません。
施行が始まっている現在、制裁金をはじめとする各種リスクを極力抑え・回避するためには、できるところから着実にGDPR対応を進め、当局等に対してGDPR遵守を対外的に説明できる状態にすることが重要です。
-
-

-
Amazonロッカーの設置場所が増えてきています
-

引用元:https://www.amazon.co.jp/ulp皆さん、何かを購入したいと思った際にネットショッピングを利用しているかと思います。
最近はなんでもインターネットで揃えることができる便利な時代。手軽に購入できるのでネットショップを利用している人も多いと思います。そんな便利なネットショッピングを利用する際に、わりと悩みになっているのが「荷物の受け取り」です。
とくに仕事やプライベートの予定で受け取りがすぐできなかった、という経験がある人も多いのではないでしょうか。ネットショップとして有名な「Amazon(アマゾン)」では、そんな受取時のストレスを軽減してくれる「Amazon Hub ロッカー」というサービスがあります!
そこで今回は、そんな便利なAmazon Hub ロッカーについてご紹介していきたいと思います。
Amazon Hub ロッカーとは
そもそもAmazon Hub ロッカーとは何かというと、Amazon専用の宅配ボックスのことです。
コンビニや商業施設などに設けられたロッカーの中、またはカウンターに荷物を届けて保管してもらい、それを受け取る仕組みになっています。Amazonで商品を購入する際に、送り先をAmazon Hub ロッカーに指定しておくことで、指定したロッカーに商品が届きます。
その指定したロッカーから、好きなタイミングで商品を受け取ることができるのです。自宅での受け取りが難しい人や、都合の良いタイミングで受け取りたい人にとってはとても便利なサービスです。
Amazon Hub ロッカー5つのメリット
自宅での受け取りができない場合に利用できる
自宅で置き配ができない場合や、受取れる人がいない場合もロッカーを使用すれば解決できます。
自分の好きなタイミングで受け取りができる
Amazon Hub ロッカーは、主にドラッグストアやスーパーマーケットなどに設置されています。買い物のついでに寄れるので、自由な時間で受取ができるのがポイントです。
配達員と会わずに受け取れる
なるべく人と会いたくない人は、非対面で受け取れ、個人名や住所などを知られることもないので安心です。
盗難の心配がない
施錠式のロッカーなので、置き配での受け取りが心配な方にもおすすめです。
家族や同居者に見られたくない商品を購入したい場合に便利
知られたくない買い物はロッカーで受け取ることで、悩みは解消されます。サプライズプレゼントを購入したいときには良いかもしれません。
Amazon Hub ロッカーのデメリット
ロッカーを利用するうえで、荷物の大きさや利用制限など下記のデメリットがあります。
利用前には、ぜひ確認しておくようにしてください。1.ロッカーに入らないほどの大きな商品は利用できない
2.ロッカーの空きがない場合がある
3.代金引換およびコンビニ・ATM・ネットバンキング・電子マネー払いは使えない
4.ロッカーが併設している商業施設が休みの場合は利用できない
5.預かり日は3日間のため、短いと感じる人もいる
6.業者によっては配達に指定できない場合があるまとめ
Amazon Hub ロッカーは、いろいろな働き方や暮らし方が増えてきた今の時代に合ったサービスの一つです。
日々忙しい時間の中で、ストレスなく荷物の受取ができるこのロッカーは、とても便利で人の生活に寄り添った新しい取り組みだと思います。
県央エリアでもツルハドラッグ燕三条店、燕小池店、三条東新保店や原信燕店など、Amazon Hub ロッカーの設置場所が続々と増えてきています。
とても便利なサービスなので、機会があればぜひ利用してみてはいかがでしょうか?
-
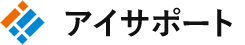
![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)