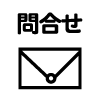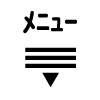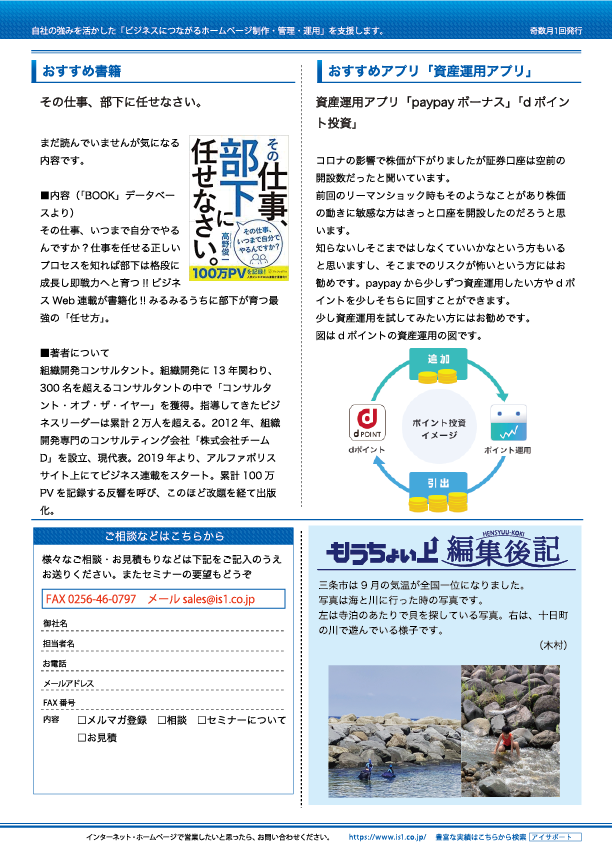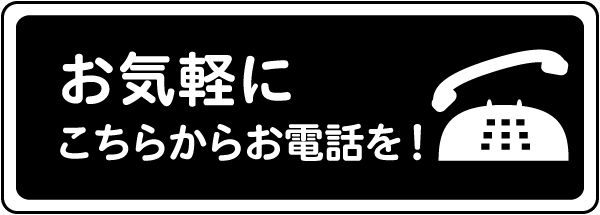ブログ
-

-
動画の掲載方法(YouTube掲載方法)
-
世の中が5Gとなり、これからますます動画の時代になると言われています。
動画を公開したいと思った場合、一番に思いつく方法は「YouTube」でしょう。
ここでは、YouTubeへ動画を掲載する方法をご紹介していきます。YouTubeにUPするための下準備
まずは、動画をYouTubeに掲載するためには、Googleのアカウントの登録と、動画を撮影しておくことが必要です。
YouTubeに掲載する方法
YouTubeに掲載する方法は、以下のような流れとなります。
動画をアップロードする
まずは、動画をYouTubeにアップロードします。
動画のアップロードでは、アップロードできる動画の容量に制限がありますので、動画を事前に編集しておくことも必要です。タイトルや説明文を入力
次に、動画のタイトルや説明文を入力します。
タイトルや説明文はユーザーが検索するときにとても重要になる要素となりますので、ユーザーが検索するであろうキーワードを入れておくと良いでしょう。サムネイル画像を設定
次に、サムネイル画像の設定です。
サムネイル画像とは、YouTubeの中で動画を表現する際に、画像として表示されるため、この画像を用意しておくことが必要です。
動画の一部を画像にすると良いでしょう。公開方法、公開日を決める
公開方法とは、公開する相手がURLを知っている人全員にするのか、特定の人にするのかなどを決めるというもので、公開日はいつから見れるようにするのかを決めるものです。
動画の掲載容量を増やすには
動画の掲載用量は、15分を超えるものはできないという制限があります。
ただし、Googleアカウントで本人認証をとれば、最大12時間の動画もアップロードできるようになりますので、まずは本人認証を取ることがおすすめです。まとめ
ここまで、YouTubeに動画をアップロードする方法をご紹介してきました。
動画のアップロードは難しいものではありませんが、まずはGoogleのアカウントを取るところから始めて観ましょう。
また、動画は撮影するだけではなく、加工・編集できるようにしておきましょう。
-
-

-

-
メールアドレスをページに載せるリスク、メリットと載せ方
-
会社のホームページに、メールアドレスを載せることを躊躇している方も少なくないでしょう。
メールアドレスを載せることでデメリットに感じることが多いという方もいると思いますが、表現方法でそのようなリスクを回避できます。
ここでは、ホームページにメールアドレスを載せる方法やメリットをご紹介していきます。メールアドレスをホームページに載せるとリスクがある?
メールアドレスをホームページに載せることで、どのようなリスクがあるのでしょうか。
1つは、スパムメールというウイルスメールが送られてくること、そして営業メールが送られてくることなどのリスクがあります。メールアドレス掲載の方法
メールアドレスを掲載する場合に、どのような工夫をすれば良いのでしょうか。
まずは、アドレスの表現を工夫するという方法があります。
例えば、@マークの代わりに■と表現したり、●と表現したりすることで、コンピューターが自動でメールを送ってくるということは比較的防げるでしょう。
また、プログラム言語でメールアドレスを表現することで、文字情報としてコンピューターが認識せずに、ウイルスメールなどが送られてくることを防ぐことができるでしょう。画像やQRコードにする
メールアドレスを画像で表現したりQRコードにしたりすることで、迷惑メールやウイルスメールを防ぐことができるでしょう。
メールアドレスを載せるメリットはあるの?
メールアドレスを載せるリスクがあることがわかりましたが、なぜメールアドレスを載せるべきなのでしょうか。
それは、問合せに繋がる可能性があるからです。
メールアドレスが表記されていることで、ユーザーが安心してメールすることができたり、問合せフォームに入力してくれるようになったりします。まとめ
ここまで、ホームページにメールアドレスの表記をする方法や、メリットについてご紹介してきました。
メールアドレスを表記することで、リスクもありますが、メリットもありますので、迷惑メールなどが来ないような工夫をして表現すると良いでしょう。
-
-

-
SNSも書いた方がいいですよ
-
マーケティング活動においてまだSNSを利用してないという企業も少なくありません。
SNSを活用する時、どのようなメリットがあるのか、どのように運用するべきかわからないという企業も多いでしょう。
ここでは、SNSをマーケティングで利用するメリットや成功するポイントをご紹介していきます。SNSを利用するメリット
SNSを利用するメリットから確認していきましょう。
認知を高められる
SNSを利用してマーケティング活動をするメリットとして挙げられるのは、認知を高めるというところです。
Webサイトを利用したWebマーケティングだけでは、多くのユーザーに認知してもらうことは難しく、検索だけでは認知フェーズの多くの消費者には情報は届きません。顧客とつながり続けられる
SNSの良いところは、情報発信だけではなく、ユーザーとつながり続けることが可能というところです。
一度購入したユーザーも、そうではないユーザーも、SNSを通じて繋がり続けることができるため、情報発信をし続けることで、中長期的に考えると認知フェーズのユーザーから購入を検討するフェーズまで引き上げていくことや、リピーターとして獲得していくためのアプローチも行えます。SNSはどのように活用するべきか
SNSを上手に活用するポイントについても見ていきましょう。
ターゲットに合わせてSNSを選ぶ
SNSはfacebook、Twitter、TikTokやInstagramなど多くのプラットフォームが存在します。
ターゲット層に合わせて、その層が利用しやすいSNSを選択してアプローチすることで、ターゲットとなる顧客に対して効果的なアプローチができます。
例えば、facebookは40代や50代の男性が利用するケースが多く、Instagramでは20代30代の女性が利用することが多いため、そのようなターゲットへのアプローチが望ましいでしょう。炎上するような内容は発信しない
SNSは拡散されて良い効果を生むこともありますが、一方で使い方を誤ると、発信した情報に対してマイナスな影響を及ぼすこともあります。
特に、「炎上」になるような発信は避けましょう。SNSを成功させるポイントは「一貫性」
SNSを利用したマーケティングを成功させるポイントは、一貫性を持たせることです。
例えば、Instagramなどでは、風景や食べ物、飲み物、商品などをバラバラに発信するよりも、食べ物なら食べ物の配信をすると一貫性を持たせることで、フォロワーも増えるでしょう。まとめ
ここまで、SNSを利用したマーケティングについてご紹介してきました。
ブログ同様にSNSも企業としては利用するべきツールと言えるでしょう。
-
-

-
ブログを書いた方がいいですよ
-
企業ブログをしっかり書いていますか?
コンテンツマーケティングという言葉が中小企業でも耳にするようになった現代において、企業ブログは企業のマーケティング活動として欠かせない手法となりました。
ここでは、企業ブログについてご紹介していきます。企業ブログとは
企業ブログとは、その名の通り企業が発信しているブログです。
その目的は、集客活動であり、認知を高めるということにあります。
しかし、ブログを書くと決めた場合には、継続して書く必要があり、中長期的にブログを使ってマーケティングすることがおすすめです。ブログを書くメリット
ブログを書くメリットについて改めて確認していきましょう。
認知フェーズのユーザーを取り込める
ブログを書くメリットとしては、認知フェーズのユーザーへアプローチでき、取り込めるという部分があります。
認知フェーズとは、まだ自社のことやサービスのこと、商品のことを知らないユーザーに対して、自社のサービスや商品を認知してもらうことができるというものです。
商品の紹介をするだけのサイトでは、商品の名前やサービス名を知らないユーザーは知ることができないため、このようなブログが有効です。ナーチャリングできる
ナーチャリングとは、顧客の育成です。
ブログを書くことによって、専門的な知識を発信し、情報提供することで顧客は知識を付けることができ、顧客になりえないユーザーを顧客になりえるユーザーまで引き上げることができます。
例えば、クロールができない人に対して「背泳ぎ」のことをアプローチしてもユーザーには響きません。バタ足や手の使い方を教えることでクロールができ、背泳ぎのアプローチができるようになります。ブランディングできる
ブランディングとは企業のブランド力を高めるということですが、ブログで情報発信をすることによって専門性の高い企業という認知をさせることができ、企業のブランド力をアップさせることができます。
「このことなら、専門的なブログを発信しているあそこに頼もう」ということになります。ブログを書くなら専門性を持たせよう
企業ブログを書くなら、ただ日記のようにスタッフの日常を発信するよりも、専門性の高い、素の企業じゃなければわからないようなことをブログとして発信することで、その業界に興味のある方や顧客になりえる方を集めることができるでしょう。
まとめ
ここまで、企業ブログを書くメリットについてご紹介しました。
企業ブログを運営するには、中長期的に継続することと、専門性の高い記事を書くことがおすすめです。
-
-

-
毎月の売り上げを安定化させたい
-
どのような企業でも、毎月の売上を多く獲得したいと思ったり、安定させたいと思ったりすることでしょう。
ここでは、毎月の売上を安定させるための考え方についてご紹介していきます。売り上げの考え方について
売り上げは、どのようにして成り立つのでしょうか。
それは「単価」×「数量」です。
単価とは、顧客の購買に関する平均単価であり、数量は人数や購買数を指します。
これらを安定させ、定期的な売上獲得をするにはストックビジネスという考えが必要です。ストックビジネスのメリット・デメリット
ストックビジネスのメリット・デメリットを見ていきましょう。
ストックビジネスのメリット
ストックビジネスを行う上で、メリットになるのは、やはり安定的な売り上げを得られるというものです。
いわゆる「ちゃりんちゃりん」ビジネスで、毎月定期的な収入があることは、企業にとっては先々の計画も立てやすく、別のことにチャレンジもしやすい組織を作ることができるでしょう。ストックビジネスのデメリット
デメリットとしては、ストックビジネスを成り立たせるまでにかかる期間やコストが大きいということです。
人件費や開発費など、固定費なども掛かるため、上手くいかせるためには長い期間が掛かること、コストが掛かることがデメリットです。ストックビジネスを構築するには
ストックビジネスの代表的なモデルには「サブスクリプションモデル」があります。
サブスクリプションモデル
サブスクリプションモデルとは、定期購入を指し、有名な企業でいえば、Microsoft社は、有名なExcelやWordを一括購入という形ではなくOffice365という月額利用での提供スタイルに変えています。
このような定期利用のことをサブスクリプションモデルと言い、ストックビジネスの代表例です。リピーターの獲得
または、既存顧客に定期的にリピーターになってもらうということも一つの方法です。
顧客数をある程度獲得できている企業では、そこから定期的にどれくらいの期間でリピートしてもらうかを戦略的に行うことで、ストックビジネスは成り立つでしょう。
美容室なんかもそのようなビジネスモデルの一つです。まとめ
ここまで、ストックビジネスについて、メリット・デメリットやストックビジネスを構築するための方法などをご紹介してきました。
これから売り上げを定期的に安定的に獲得していくためには、どのようなサブスクリプションモデルのビジネスができるか、企業ごとに検討してみると良いでしょう。
-
-

-
QRコード活用方法
-
マーケティング活動において、デジタルマーケティングに注目されていますが、デジタルだけがマーケティング活動の全てではありません。
非デジタルとデジタルを融合させたマーケティングはどのような企業にも必要と言えるでしょう。
今回は、そんなマーケティング活動におすすめの「QRコード」の上手な使い方についてご紹介していきます。QRコードをうまく活用していますか?
QRコードはかなり前から使用されているものですが、スマートフォンの利用者層が広がってきている中、QRコードは馬鹿にできないものです。
企業のマーケティングにQRコードを上手に利用できているでしょうか。QRコードを上手に利用する方法
QRコードを上手に利用する方法としては、デジタルマーケティングの強みである「解析」をしっかり行うことです。
それぞれにパラメーターを付ける
QRコードをチラシやはがきなどにつけマーケティング活動をする場合、その移動先のWebページURLにパラメーターを設置することです。
パラメーターとは印のようなもので、「このQRコードから訪問している」ということを後からわかるようにするものです。アクセス解析する
QRコードにパラメーターを付けることで、はがきからサイトに訪れたのか、チラシから訪れたのかがわかるようになり、そこからのコンバージョン率などを計測することで、マーケティング活動においてどのような媒体に効果があるのか、コンバージョンに繋がるのかを見極めることができ、生産性の高い、費用対効果の高いマーケティング活動ができます。
デジタルマーケティングのポイントは解析し最適化すること
デジタルマーケティングにおいて成功させていくためのポイントは、解析をすることからはじまります。
解析し、ターゲットとなるユーザーがどのような行動をするのか、どのようなニーズがあるのかを見える化し、そこからマーケティング活動を最適化していくことで、生産性の高い事業運営ができるでしょう。
そのためには、まずは解析から始まるため、どこから来たのか、どのような媒体に効果があるのかを計測できるQRコードの活用がおすすめです。まとめ
ここまで、QRコードについて、マーケティング活動におけるおすすめの使い方をご紹介してきました。
QRコードをはがきやチラシに付けている企業も多いと思いますが、そこから解析していくことで、ターゲットとなる顧客の行動が見えてきます。
まずは、解析するところから始めてみてください。
-
-

-
ファビコンのメリット
-
ファビコンという言葉を聞いたことがあるでしょうか。
Webサイトを構築するコーダーの方や、制作会社の方であれば目にしたり耳にしたりしたことがあると思いますが、企業のWeb担当者レベルの方は、あまり普段から意識しない部分かもしれません。
今回は、「favicon(ファビコン)」についてご紹介していきます。ファビコンとは
ファビコンとは、Webサイトに訪れたユーザーのブラウザ上に表示されるアイコンのことで、サイトタイトルはブラウザのタブ部分に表示されますが、その隣にあるのがファビコンです。
何も設定されていない場合には、デフォルトのアイコンが表示されるようになっています。ファビコンを設置するメリット
ファビコンが設置されるとどのようなメリットがあるのかを確認していきましょう。
視認性が高まる
視認性とは、ユーザーが見たときに「何があるか」「どこにいるか」「どんなサイトか」というものを瞬時に判断させるもので、ファビコンが設置されていることで、「私は〇〇のサイトにいる」ということを認識させることができます。
もちろん、ファビコンだけではなくそれ以外の部分でも重要な点はありますが、ファビコンはその一つの要素になるでしょう。信頼性が高まる
ファビコンが設置されることで、「このサイトは私が思っているサイトだ」というように、サイトの信頼性が高まります。
Webサイトは世の中にたくさんあり、その中には悪質なサイトも存在するため、自分がどのサイトにいるのかを確認しているユーザーも多く存在します。
そのような場合に、ファビコンは信頼性を高める一つのポイントになるでしょう。ファビコンの作り方
ファビコンは、Photoshopなどの画像加工ソフトでも、Webサイトのサービスでも作成できます。
ポイントとしては、サイズを確認することと、ファイルのフォーマットを「ico」で書き出す必要があるということです。
また、作成をする上で注意したいのは、視認性の高いファビコンにするということで、見たときにすぐパッとわかるものにすることが必要です。
NTTなどは「NTT」というファビコンではなく、NTTのロゴマークがファビコンとして使用されているなど、見やすさの工夫がされています。まとめ
ここまで、ファビコンについてご紹介してきました。
ファビコンは、すぐに作成できるのに設置していないサイトも多く存在します。
Webサイトを制作したら、まずはファビコンの設置も忘れずに行いましょう。
-
-

-
上位表示に結び付くコンテンツ
-
SEO対策をしているWeb担当者なら、コンテンツSEOという言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
コンテンツを利用してSEO対策をすることは、今では多くの企業が行っています。
そこで、今回は上位表示に結びつきやすいコンテンツとはどのようなものかをご紹介していきます。コンテンツSEOについて
まずは、コンテンツSEOについて理解していきましょう。
コンテンツSEOとは、コンテンツ、つまりWebサイトのページを一つのコンテンツとしてマーケティングをするというもので、SEO対策の一つとして、コンテンツを利用した対策を行うというものです。
コンテンツSEOは、その名の通りコンテンツ作りが重要です。コンテンツ作りのポイント
良いコンテンツ、SEO対策になるコンテンツとはどのようなものでしょうか。
見ていて「面白い」と思われるコンテンツ
コンテンツの良い例としては、閲覧していて「面白い」と思わせるものです。
面白いとは、笑わせるというものではなく、読んでいて読み物として面白いと感じたり、情報の内容が面白いと思われたりするものです。
コンテンツは「読んでもらうこと」がポイントとなるため、まずは興味が湧く内容にしなければなりません。情報の内容に専門性があるコンテンツ
Googleがポイントにしているものの一つに「専門性」があります。
例えば、医療のものであれば医師が提供している情報、法律に関しての内容であれば弁護士が監修している内容などが、専門性が高いと言えるでしょう。どこにもないような情報があるコンテンツ
世の中に「ここにしかない」という情報があれば、間違いなく良いコンテンツと言えるでしょう。
情報の専門性や希少性などは、Googleが望むコンテンツとなるため、そのようなコンテンツを作ることが望ましいでしょう。コンテンツSEOは中長期的に行うこと
コンテンツSEOは、今日実施して明日結果が出るというものではありません。
中長期的に考えなければ結果に結びつかないため、コンテンツSEOでは、長期的な戦略を立てることが必要です。まとめ
ここまで、SEO対策に必要な良いコンテンツとはどのようなものかをご紹介してきました。
コンテンツSEOは、中長期的な戦略が必要となり、コンテンツの内容としては、専門性があるものや、希少性のあるもの、そして読み物として面白さが必要であるということをご紹介してきました。
これからコンテンツ作りをしようと思っている方は、是非参考にしてください。
-
-

-
「ドメイン」と「サーバー」について
-
ホームページを作成しようかな?と思ったときに「ドメイン」のお話を聞いたことはあるかと思います。
ホームページを作成・公開するには、「ドメイン」と「サーバー」が必要になります。■ドメインとは
ホームページに名前をつけてPRすることができるのですが、そのアルファベットと英数字のことをドメインと言います。会社に例えると「社名」「屋号」にあたります。
そのまま、社名をつける場合もありますし、屋号のように「サービス名+社名」をつける場合もあります。
また、1つの会社で複数のドメインを使用する場合もあります。例えば、日産の場合は、車の情報が掲載されているホームページはがnissan.co.jp、会社情報はhttps://www.nissan-global.com/ になります。
最近は中小企業でも上記のように使い分ける例も増えています。
また、ドメインは固有のものですので、違う会社が同じドメインを持っているということはありえません。そのため独自ドメインと言われる場合もあります。
■ドメインの最後の文字について
https://www.●●●●●●●●.com/ などのようにcom やco.jp やjpなどがあります。
この部分はセカンドドメインと言われています。同じようなのaaa.com とaaa.jp でも最後のcomとjpが違う場合、違うホームページになります。
また、comやjpなどの種類によって法人形態により取得できない場合などがあります。co.jp ・・・日本の法人しか取得できない。1つの法人で1つの契約しかできない。
jp・・・個人・法人の取得できる。1つの法人で複数の契約ができる。などあります。さらに最近は登録できるドメインの種類も増えています。
■ドメインを取得するのメリット
・ドメインから社名やサービス名を覚えてもらえる。
名刺や会社案内などに記載しますので、そこから覚えてもらえます。
また、サービス名をドメインにすることで、サービスの特徴も覚えてもらうことができます。・ドメインと連動したメールアドレスを持つことができる。
下記のように@(アット)マークから左側は自由に設定することができます。
名前だったり部署名をつける場合が多いようです。例:info@google.co.jp など
■サーバーについて
・サーバーはインターネット上にホームページを公開するためにデータをいれておく箱のようなものです。
また、社内にサーバーがあるという企業から、これを利用できないかとたまに言われますが、社内のサーバーとインターネット上に置くサーバーは別なものになります。
実は、同じサーバーを利用することは可能ですが、インターネット上に公開することになりますので、非常に危険な状態になりますのでお勧めはしません。・サーバーにさまざまな設定を行うことでいろいろな情報を取得できます。
ドメインを取得しサーバーを設定することで、インターネット上の様々な情報を取得できるようになります。
その情報を利用して営業や作業効率アップに繋げていくことが可能になります。
-
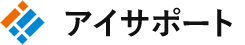
![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)