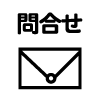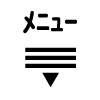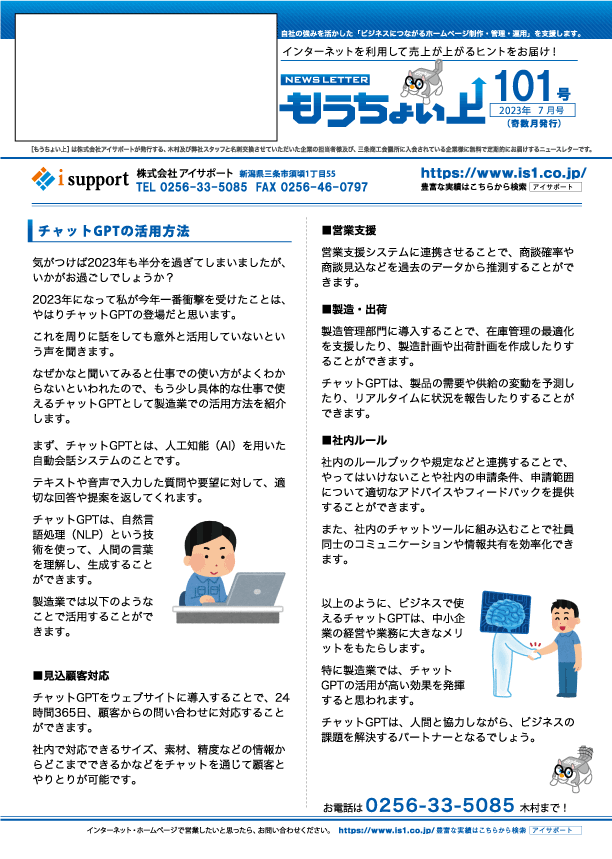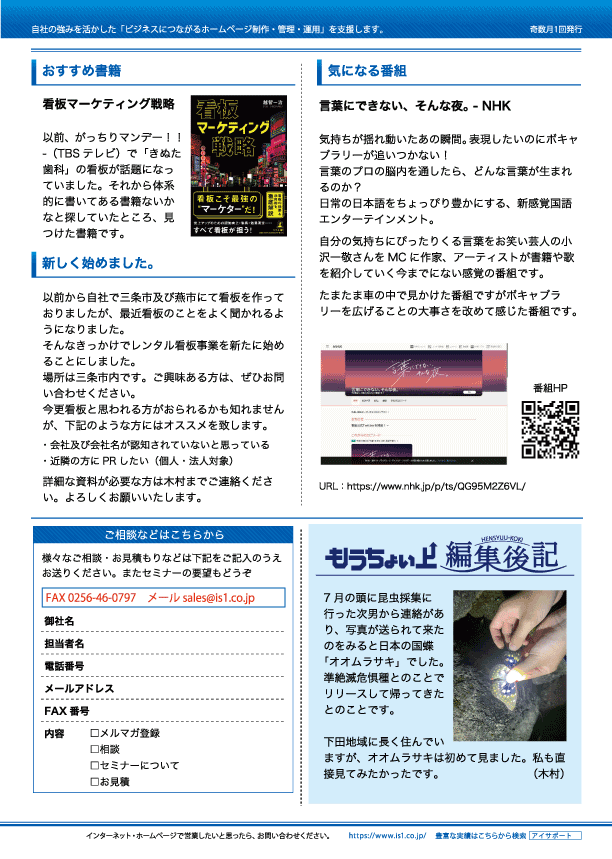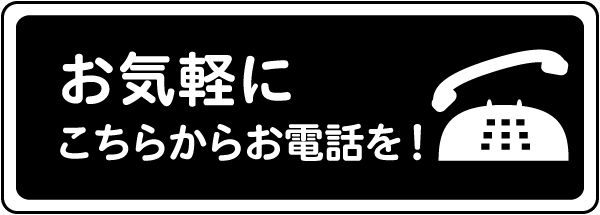ブログ
-

-
レンタル看板サービスはじめました
-
アイサポートでは新しくレンタル看板サービスを開始しました!
看板のデザイン、制作・設置まで対応しております。
看板は、お店や会社の住所・サービス内容を正しく知らせ、誘導をスムーズにするなど、集客・エリアマーケティングには欠かせない戦略ツールです。
必要な人に必要な情報をお知らせして知名度や集客、売上をアップするお手伝いをさせていただきます。・お店を新規オープンしたけど、場所がメイン道路の路地を入ったところにあるので目立たないしわかりづらい…
・商圏を広げたいと思っているけど、どうすればたくさんの人に認知してもらえるのかわからない
・新しいサービスをはじめるので、会社の認知度アップに効果的な看板を立てたいこんなお悩みがありましたら、アイサポートのレンタル看板サービスをぜひご活用ください!
看板設置のメリット
看板広告で集客率アップ
看板には「認知・宣伝・誘導」の3つの役割があります。
看板の前を通った人々に、お店や会社の存在を知ってもらい、魅力を伝え、足を運んでもらうことが主な役割で、戦略的な集客アップやイメージアップなどが期待できます。看板広告で売上アップ
周囲と比べて目を引くデザインや看板に載せる情報をわかりやすく整理します。
通りかかる人の目線や読みやすさを重視した看板制作をご提案させていただきます。24時間365日設置可能
看板広告は24時間365日ずっと広告を掲示することが可能なため、4大マスメディア(テレビ・ラジオ・新聞・雑誌)やインターネット広告よりも広告料が安価であり、中長期のプロモーションに適しています。
広告ターゲットの生活動線上に広告を設置できるので、認知拡大や宣伝目的にはぴったりです。看板広告は車社会に適応した広告
走行中の車やバイクに視認させる広告として、在来手法の看板広告が最も適しています。
沿道に設置されることの多い看板広告は、基本的に移動中に見られます。看板広告は広告表示が変わるということがないため、走行中の車やバイクから視認する際に、より長く広告面を見ていただくことができます。ご利用の流れ
お申し込み
まずはお問い合わせフォームまたはお電話より、お問い合わせください。
ご相談だけでも問題ありません。お気軽にご連絡ください。デザイン作成
設置した看板のデザインを作成します。
看板のデザインはお客様の方でご用意いただくか、弊社の方でデザインを作成させていただきます。ご契約
基本は複数年契約になります。
短期間の掲載も承りますので、ご相談ください。設置
掲載場所の看板に広告を掲載いたします。
1ヶ所のみの掲載でも、複数場所での掲載でも、どちらも対応可能です。
-
-

-
メルマガの効果やメリットについて
-

メルマガとは、自社のお客さまリストに対して定期的にメールを送信するメールマーケティング手法の1つです。
メルマガを始める前に「メルマガの効果って具体的にどういうもの?」「どのようなメルマガなら効果が出るの?」といった疑問を抱くこともあるのではないでしょうか。
今回はメルマガを始めるか検討している方向けに、メルマガの効果やメリットなどについてご紹介していきたいと思います。メルマガの3つの効果
関係性強化
メルマガの1つ目の効果は、関係性強化です。
関係性強化とは、メルマガの継続配信で定期的にお客さまと接点を持ち、自社や自社の商品、サービスのファンになっていただくことです。
メルマガでお客さまとの関係性を強化するには、読者にとって役立つ情報を提供し、好感を持っていただくことが大切です。売り込みの強い内容だけでは関係性強化にはつながりません。
「業務や生活に役立つ情報」や「自社や自社のサービスの歴史や想い」といった内容のメルマガは、お客さまとの関係性強化につながります。認知度向上
メルマガの2つ目の効果は、認知度向上です。
素晴らしい商品やサービスも、市場での認知度が低いと買っていただけません。メルマガは、サービスの認知度を向上させる手法の1つです。
特に、サービスの認知度が低い場合や、多機能で理解が難しいサービスを取り扱っている場合は、自社サービスを紹介するメルマガを送ることで、認知度の向上を見込めます。
「自社の商品・サービスの魅力」、「導入事例」などといった内容のメルマガは商品やサービスの認知度を向上させることができるでしょう。販売促進
メルマガの3つ目の効果は、販売促進です。
販売促進のためには「キャンペーン情報」や「クーポン配布」、「セミナー情報」、「展示会の案内」などといったメルマガが効果的です。
キャンペーン情報や商品宣伝のメルマガばかりを送りすぎると、読者から「売り込みの強いメルマガだ」と思われ、敬遠されてしまいます。販売促進の効果を狙ったメルマガは、単発的に配信するのがおすすめです。メルマガの3つのメリット
費用対効果がよい
メルマガは、費用対効果がよいマーケティング手法です。
ダイレクトメールのように紙媒体のマーケティング手法では、製作費や輸送費がかかり、デザインの知識も必要です。くらべて、メルマガにかかるコストはツール利用料金程度のため、数千円から数万円です。
ダイレクトメールと違い、配信数が増えても、金額が上がることはありません。安価でお客さまと定期接触を図ることができ、費用対効果のよい点がメルマガの強みです。読者に合ったコンテンツを届けられる
オウンドメディアなどのWeb上のコンテンツは、「誰に読んでいただくか」を執筆者は選択できません。
しかし、メルマガは配信リストを「業種」「地域」「ニーズ」などで分類し、分けて配信できるため、「誰に読んでいただくか」を選択することができます。
読者の興味・関心に合わせて内容を送り分けたメルマガは、一斉送信に比べて開封率やクリック率が高くなる傾向があります。読者の受信箱に保存され、いつでも検索可能
掲載期間が終了したら閲覧できなくなる広告と違って、メルマガは顧客の受信箱に保存され、いつでも検索できます。
実際に、半年前のメールに返信があり、商談に繋がったケースもあります。
半年前に送ったメルマガに返信が来た理由は、メルマガが「検索可能」で、「受信箱に保存される」性質を持っていたからです。メルマガを始める前に知っておきたい注意点
メルマガを配信するには、お客さまのメールアドレスが必要です。
メールアドレスは当然個人情報に該当するので、流出には注意しなければなりません。
個人情報を流出させてしまうと、「個人情報保護法」に抵触します。
個人情報の流出を防ぐ方法は、メール配信ツールやマーケティングオートメーションなどの、メール配信に適した専門のツールを利用することです。また、メルマガはすぐに効果が出る施策ではない、ということをあらかじめ理解しておくようにしましょう。
もちろん、メルマガを始めたばかりの頃はリストが新鮮なため、「興味あります」という問い合わせも多くいただけるかと思います。ただし、自社商材への興味関心が顕在化している層に向けた宣伝ばかりの配信を続けていると、配信解除が増え、リストが枯渇してしまいます。
メルマガは、お客さまと継続的に関係性を築いていく、時間をかけるべき施策だと理解し、長期的な目線で始めましょう。もし、すぐに効果を出さなければならない状況であれば、メルマガ以外の施策も検討しましょう。まとめ
今回はメルマガの効果、これからメルマガを始める際の注意点、知っておきたいことなどについてご紹介しました。
メルマガを始めるか検討している方は、ぜひ上記の内容も参考にしていただければと思います。
これからメルマガを始めたい!とお考えの方はアイサポートまでお問い合わせください。
-
-

-
ヒートマップとは
-
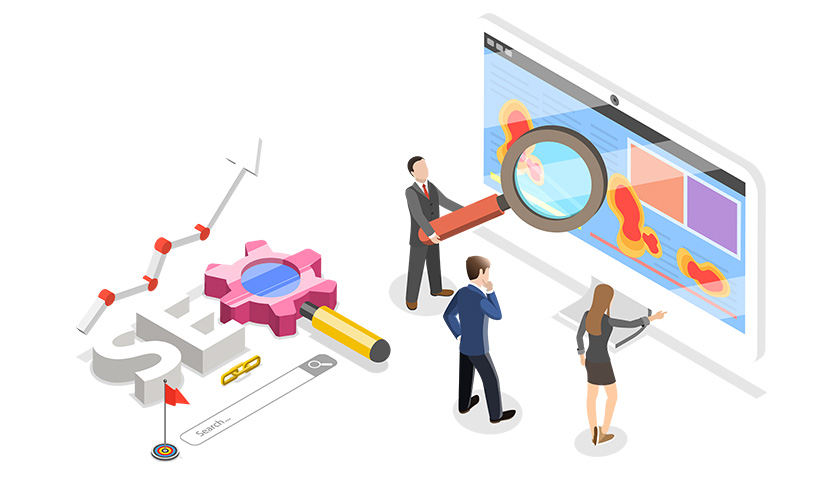
ヒートマップを使ってWebサイトの分析をしたい人の中には、Microsoft社が提供している無料でありながらも優秀なヒートマップツール「Microsoft Clarity」を使ってみたい、そもそも何ができるのか知りたい、使い方を知りたいといったことを考えている人もいるのではないでしょうか。
今回はヒートマップについて、「Microsoft Clarity」の機能面やメリットなどについてご紹介していきたいと思います。ヒートマップとは
ヒートマップとは、WEBサイト内でユーザーがどのコンテンツを見ているのか、どこをクリックしているのか、どこで離脱しているのか、などのアクションを色で可視化したアクセス解析ツールです。
ヒートマップは人間の体温を視覚的に見ることができるサーモグラフィに例えると、アクションが集中している部分は温度が高くなるように、アクションが集中していない部分は温度が低くなるように見えます。
ヒートマップを使うと、ユーザーがどこまでスクロールして離脱したのか、ページ上のどの部分を読んでいるのか、どこをクリックしているのかなどといったことがわかります。Microsoft「Clarity」とは
Clarityについて
Microsoft「Clarity」とは、Microsoft社が提供している無料のヒートマップツールのことです。
Webサイトを訪問したユーザーが、ページ上でどの部分を見て、どこをクリックしたのかということが分かるツールで、サイトコンテンツの分析に役立ちます。Clarityに備わっている機能
・ヒートマップ機能
Clarityのヒートマップ機能は、アクセスしてきたデバイス、国、期間などのフィルターで結果を絞り込んで表示できます。
また、クリック位置のデータの他に、「スクロール」項目で何%のユーザーがどこまで画面をスクロールしたかが分かる機能や、「領域」項目で何%のユーザーがどこをクリックしたのかが分かる機能も備わっています。・レコーディング機能
レコーディング機能とは、Webサイトを訪問したユーザーの実際の動きを記録し、動画データとして記録する機能のことです。
ページの滞在時間やマウスカーソルの動き、クリックした場所、スクロールの流れといったユーザーが実際に動いた様子が視覚的に確認することができます。・ダッシュボード
ダッシュボードとは、Webサイトに訪問してきたユーザーに関する情報をまとめて表示させたページのことです。
Clarityのダッシュボードでは、アクセス数や1アクセス当たり何ページ見られているか、ユーザーの平均滞在時間のほかにデッドクリック率(ページを効果なくタップまたはクリックしたユーザー)やクイックバック率(ユーザーがページに移動した後、前のページに素早く戻る)といったユーザーとって評価の悪いページがどこなのかを知ることができます。Clarityを使うメリット
無料で使うことができる
ヒートマップツールは有料無料を問わず数多くのツールが存在しますが、無料で使えるツールは少ないです。
「ヒートマップとはどういうものなのか」「Clarityの使い勝手を試したい」という人も、まずはお試しで気軽に始めることができます。Googleアナリティクスと連携可能
Clarityは、Googleアナリティクスと連携が可能です。
ClarityとGoogleアナリティクスを連携させることで、Googleアナリティクス上でClarityが持つデータの一部を参照できたり、逆にClarity上でGoogleアナリティクスのデータの一部を参照できたりします。データの保有期間に制限がない
Clarityは無料のツールでありながら、データの保有期間に制限がありません。
そのため、長期的なアクセスデータを無料で解析することができます。まとめ
今回はMicrosoft「Clarity」の機能やメリットについてご紹介しました。
Clarityは無料で使えるヒートマップとして、非常に質の高いツールで、レイアウトも分かりやすく、機能的にもユーザーの導線を分析するために十分なものが備わっています。
ぜひ自社のWEBサイトの分析でヒートマップを使ってみたいと思われましたら、アイサポートまでご相談ください。
-
-

-
GA(UA)が2023年7月にサポート終了、GA4への移行は完了しましたか?
-

2023年7月1日をもって「旧Google Analytics(ユニバーサルアナリティクス)」が終了となりました。
今回はGoogleアナリティクスの最新バージョンである「Googleアナリティクス 4 プロパティ(GA4)」について、改めてご紹介したいと思います。GA4について
GA4(Googleアナリティクス 4 プロパティ)とは、Googleアナリティクスの最新版です。
Googleアナリティクスとは、Googleが無料で提供する解析ツールです。
多くのマーケターが活用している最もスタンダードなツールで、Webサイト内のユーザー行動や、ユーザーがどういった経路でサイトに訪れたかといったデータを計測でき、サイト分析に活用できます。UAとGA4の決定的な違いは、「分析軸」の違いにあります。
GA4になったことで、「セッション」から「ユーザー」に分析軸が移行しました。
従来のバージョン(UA)では、「セッション(訪問)」が重要な指標で、セッションを軸とした計測がメインでしたが、GA4ではユーザーを重視する計測に変わりました。
「どういうユーザーにサイトに来てもらうべきか?」を分析し、自社にとって「本質的なお客さまに来てもらえてるのか?」「正しいお客さまを呼べてるのだろうか?」という視点で分析するツールとなりました。GA4になって変わったこと
UAからGA4になって変わった点は、細かいところを含めると非常に多いです。
具体的な変更点についていくつかご紹介させていただきます。ダッシュボードのUIがリニューアル
GA4では、ダッシュボードの見た目が大幅に変更され、UIがリニューアルされました。また、左側にあったメニューの内容も変更されています。

分析指標が「イベント」単位になった
今までは「セッション」を指標としていましたが、GA4では「イベント」を指標とする計測に変わりました。
「イベント」とはつまり「ユーザーのアクション」のことで、ユーザーが何かしらアクションを起こすと、「イベント」として計測されます。ポート構成が大幅に変わった
GA4で大きく変化した箇所に「レポート」があります。構成も画面も大幅に変わりました。

GA4になったことについてのポイント
今まで利用していた旧Google Analyticsのデータ計測は2023年7月1日をもって停止されています。
また、2024年1月1日から順次、旧Google Analyticsのデータは見れなくなります。
旧Google Analyticsの過去データはGA4へ移行はできませんので、ご注意ください。GA4への移行のメリットや移行時の注意点など、過去の記事で紹介していますのでまだ移行されていない方はぜひご一読ください。
https://www.is1.co.jp/staff-blog/20220509.htmlまとめ
2023年7月1日をもって旧Google Analyticsは終了しました。
当社と保守契約されているお客様はGA4移行済みです。
保守契約をされていないお客様の中で、まだGA4を設定されていない場合は当社にて設定可能ですので、ぜひ気軽にご相談ください。
-
-

-
2023年8月:補助金・助成金最新情報
-

補助金や助成金は、国や自治体が産業振興や雇用の推進、地域活性化などに貢献する事業に対して交付する資金のことを指します。
潤沢な資金が用意しづらい場面が多い中小企業や個人事業において、有用な資金調達手段の一つです。
新潟県燕市、三条市を中心に現在実施されている補助金・助成金の一部をご紹介します。小規模事業者持続化補助金
小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス制度の導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
【補助対象者】
・小規模事業者であること
・資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
・確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと 等
【支援内容】
上限額:[通常枠]50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
補助率:3分の2以内(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は4分の3)
【実施機関】商工会議所、全国商工会連合会
【詳しくはこちら】
https://r3.jizokukahojokin.info/
https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/新事業チャレンジ補助金
エネルギー・原材料価格高騰の影響を踏まえ、中小企業等が経済社会活動の変化に対応するために行う新たな商品開発やサービスの提供、またはDXや脱炭素等に関する前向きなチャレンジを支援するものです。
【補助対象者】
・県内中小企業であること
・一般型については、売上減少要件に該当する事業者であること
【支援内容】
一般型
・補助率 2分の1以内
・補助金額上限 100万円(補助対象事業費200万円)
・補助金額下限 10万円(補助対象事業費20万円)
重点型
・補助率 3分の2以内
・補助金額上限 133万3千円(補助対象事業費200万円)
・補助金額下限 13万3千円(補助対象事業費20万円)
【実施機関】新潟県
【詳しくはこちら】https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/chiikishinko/challenge202102niigata.html中心市街地空き家改修事業等補助金(新規出店事業)
近年の急速なモータリゼーションの進展、消費者のライフスタイルの多様化や郊外型大型店の増加などによる影響、また事業者の高齢化や後継者不足による廃業などが原因となり、年々空き家が増加する傾向がみられています。
空き店舗が増加すると、来街者の減少やにぎわいの喪失にさらに拍車をかけるという悪循環につながり、早急な対応が必要とされています。
三条市では平成27年度から対象を拡大し、これまで以上に幅広い層への新規出店を促し、中心市街地における空き家、空き店舗の解消を更に進めてまいります。
【支援内容】
1.改修費
・補助率:3分の2
・上限額:130万円
・補助要件:賃借料の補助を受けない場合
2.改修費
・補助率:2分の1
・上限額:70万円
・補助要件:賃借料の補助を受ける場合
3.賃借料
・補助率:2分の1
・上限額:月額5万円
・補助要件:補助期間は、1店舗につき1年を限度とする。
【実施機関】三条市
【詳しくはこちら】https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/chiikikeieika/chukathu/1022.html令和5年度空き家改修事業等補助金(新規出店事業)
三条市のまちなかで自分のお店を持ちたい方、事業を行いたいと思っている方、空き店舗等を活用して商売を始めてみませんか。
市では、中心市街地の空き店舗等に新規出店する方を応援します!
【補助対象者】
・補助対象エリア内にある空き店舗等を賃借し、新規出店する個人、法人
【支援内容】
(1)店舗改修費のみ補助を受ける場合
店舗改修費の3分の2相当額(限度額130万円)
(2)賃借料及び店舗改修費補助を受ける場合
・賃借料
月額家賃の2分の1相当額(限度額 月額5万円)
(注意)敷金、礼金は補助対象外
・店舗改修費
店舗改修費の2分の1相当額(限度額 70万円)
(注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外
【実施機関】三条市
【詳しくはこちら】https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/chiikikeieika/chukathu/1024.htmlDX販路拡大支援補助金
市内中小企業者を対象に、販路開拓を目的としたホームページや動画の作成、またはオンライン見本市等の出展事業費用の一部を市が負担し、燕市内の中小企業のDX推進を支援します。
【対象事業】
・ホームページの作成・機能強化および動画作成費用
【支援内容】
ホームページの作成・機能強化および動画作成費用
燕市内のベンダーを利用する場合:
・補助率 2分の1以内
・補助限度額30万円
燕市内のベンダーを利用しない場合:
・補助率 3分の1以内
・補助限度額15万円
【実施機関】燕市
【詳しくはこちら】https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shien/seido/shienseido/11616.htmlDX生産性向上促進補助金
IoT・AI・センサリング等の活用による業務の自動化・省力化や、ソフトウェアやクラウドサービスの導入によるバックオフィスの効率化ための事業費用の一部を市が負担し、市内中小企業のDX推進を支援します。
【対象事業】
・スマートファクトリー化
・バックオフィス業務の効率化
【支援内容】
交付要件によって変動
【実施機関】燕市
【詳しくはこちら】https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shien/seido/shienseido/11661.htmlまとめ
新潟県燕市、三条市を中心に実施している補助金・助成金の一部をご紹介しました。自身の事業で該当する補助金・助成金などがあれば、積極的に申請を検討してみてください。
※申請期間が設けられているものもあります。自身が申請する段階で、まだ申請期間内であるかを確認するようにしてください。
-
-

-

-
AIチャットボットについて
-

カスタマーセンターなどをはじめとした、これまで人力で対応してきた業務に対し、チャットボットを導入し効率化を図る企業が増えてきています。
今回はAIチャットボットの特長や導入のメリットなどについてご紹介していきたいと思います。チャットボットとは
チャットボット(chatbot)とは、ユーザーからの質問に対して、人間の代わりにロボットがテキストや音声データを用いて回答する自動会話プログラムのことです。
語源の由来は、リアルタイムで文章のやり取りを行う「チャット」と作業の自動化を図るロボットを意味する「ボット」を組み合わせた造語となっています。チャットボットにはシナリオ型とAI型の2種類があります。
シナリオ型は、ユーザーが次々に選択形式で表示される問いに回答ボタンを押していくことで、最終的に、自分の求めている回答に行き着くようにするチャットボットです。
そのため、あらかじめ質問に対する回答や質問の選択肢を用意しておく必要があります。AI型は、その名のとおりAI(人工知能)を搭載したチャットボットであり、自動返答に加えて機械学習ができることを特長としています。
AIが膨大な量のデータを学習し、そこから規則性を見つけ、判断や予測を自動で行います。この機能を活用することで、ユーザーとの会話からキーワードを拾い上げ、自動で質問と返答を推測します。
AIチャットボットは、繰り返し会話が行われれば行われるほど、データの蓄積量も増えていくので、反復学習を続けることで回答の精度もアップし、人間が対応するのと同じような自然な返答をすることも可能になります。AIチャットボットの特長・メリット
顧客対応業務を効率化できる
AIチャットボットを導入すれば、前述したとおり、従業員の顧客対応業務をロボットが代わりに行ってくれるため、業務の効率化につながります。また、従業員も少人数で運用できるようになるため、人件費の削減にもつながります。
また、24時間365日対応可能なため、これまで営業時間内にしか問い合わせできないことを不便に感じていたユーザーの満足度も向上するでしょう。幅広い問い合わせに対応できる
さまざまな問い合わせに対応できるのも、AIチャットボットの特長です。例えば、営業時間を知りたいユーザーが複数人いたとして、それぞれ「いつ開いていますか」「何時から営業していますか」「営業時間は?」などといった、同じ内容の質問であっても質問の仕方が異なる場合があります。
こういったケースにおいても、きちんと言葉のゆらぎに惑わされることなく正確に回答することができます。
機械学習の経験から、統計的に回答を導けるため、ユーザーにあわせた柔軟な対応が可能なのです。回答の精度を改善できる
AIチャットボットは、繰り返しの学習によって回答の精度を高め改善を図ります。
一度だけではすぐに最適な回答はできかねますが、会話の回数を増やし、記録データを蓄積すればするほどに精度は向上します。
最初は困難だったユーザーからの複雑な質問に対しても回答できるようになるのがメリットのひとつとなっています。AIチャットボットを導入するには
実際にAIチャットボットを導入するには、まず導入目的を明確にする必要があります。
何のためにチャットボットを導入するのか?チャットボットに期待する効果は何か?などチャットボットを導入するゴール、すなわち導入目的を明確にしましょう。次に、導入するチャットボットに最低限求める条件を選定します。
チャットボットを使う上で最低限この機能だけは搭載したい、月額○○円以内なら費用をかけられる、最短でも○○までに導入したいなど、チャットボットに求めるモノを明確化しましょう。その他にも、実際にチャットボットを設置する場所を決める、無料トライアルを利用して実際にチャットボットに触れてみる、事前にチャットボットを運用するための体制づくりを整える、といったことを導入前には行うようにしましょう。
まとめ
チャットボットを活用することで、これまで人が行ってきた作業の効率化や従業員負担の軽減、さらには顧客満足度の向上にもつながります。
チャットボットを導入してみたいけどどうしたらいいのかわからない、どのチャットボットがいいのか相談にのってほしいなどありましたら、お気軽にアイサポートまでご連絡ください。
-
-

-
企業のSNS炎上事前対策となった場合の対処法
-
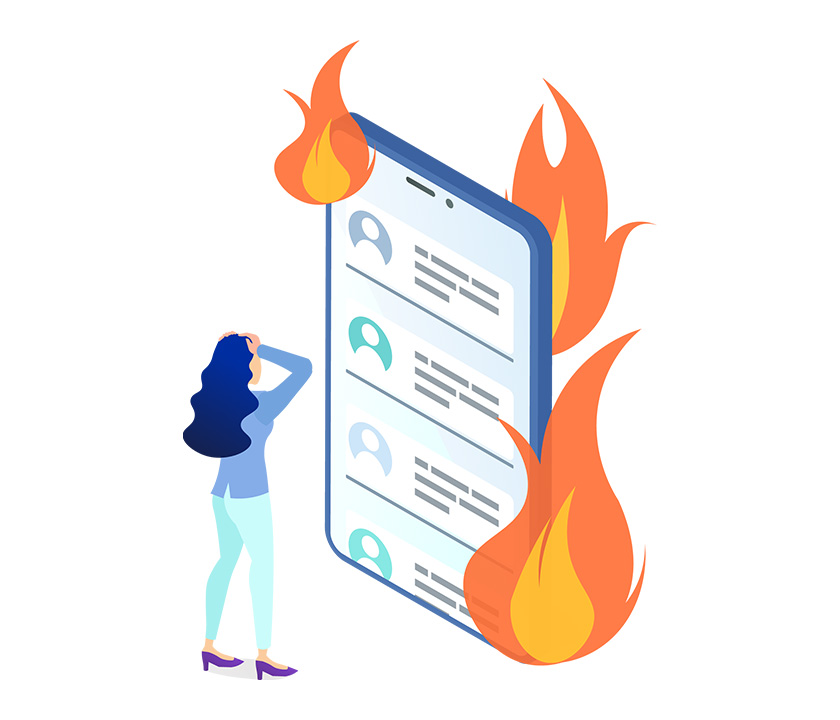
企業がTwitterやInstagram、FacebookといったさまざまなSNSを運用する上でもっとも恐れるべきなのは「炎上」です。
SNSは拡散力が強いのが魅力のひとつとして挙げられますが、好意的ではない内容がソーシャルメディア上で拡散される炎上が発生することも少なくありません。
今回は自社のアカウントが炎上しないための対策と、万が一炎上してしまった場合の対処法についてご紹介していきたいと思います。SNSにおける炎上とは
炎上とは、SNSの特定の投稿に対して批判や誹謗中傷が殺到している状態のことをいいます。
ひどい場合はSNS内にとどまらず、マスメディアやニュースサイトに取り上げられてさらに燃え広がることもあります。
企業アカウントで炎上が起こる場合は主に、政治や宗教、ジェンダーなど、センシティブな話題に触れた投稿や個人のアカウントと間違えて企業アカウントで投稿、顧客によるクレーム・内部告発で発生することがほとんどです。炎上が起こるまでの流れ
炎上は以下のような流れで起こります。
①炎上のきっかけとなる投稿が生まれる
②投稿を見たユーザーがそれについて言及・シェアする
③投稿が拡散され話題になる
④ネットニュースやまとめサイトへ掲載される
⑤テレビ・新聞などのマスメディアに取り上げられ、世間一般に認知される④まで進んでしまうと、簡単に沈静化することは難しくなるでしょう。炎上の被害を抑えるためには早期に対処することが不可欠です。
SNSの炎上対策
センシティブな話題には触れない
政治や宗教、ジェンダーなど、特定の人たちに不快感を与えかねない話題には触れないのが無難です。些細な表現をつつかれる場合もありますので、投稿やキャンペーン内のセンシティブな要素は極力排除しておきましょう。
また、特に災害時などの非常事態は人々の気が立っており、些細な投稿でも炎上しやすい傾向がありますので気を付けるようにしましょう。投稿前に複数人で内容をチェックする
いくら注意していても、自分ひとりの視点ではどうしても見落としが出てきます。
自社の投稿による炎上対策のために、投稿内容が適切かどうかを担当者ひとりだけで判断するのではなく、ダブルチェック、トリプルチェックができるようにするなど複数人で判断できる体制を構築しましょう。運用マニュアルを予め定めておく
上記2点を踏まえ、公式アカウントとして運営する上でのルールを設定しておきましょう。
アカウントの管理体制、投稿のチェック方法などはもちろん、投稿のテンプレートや使用禁止キーワードのリストなどを作っておくと効率的です。炎上が起こった場合の対処法
しっかりと対策をすれば、ある程度炎上を防ぐことはできますが、残念ながらリスクを完全にゼロにすることは不可能です。万が一炎上してしまったときは、以下を参考に落ち着いて対処するようにしましょう。
まず原因を特定する
炎上した際にいきなり投稿を削除すると、「逃げた」と言われさらに炎上が盛り上がることがあります。
場当たり的な対応をせず、落ち着いて事実確認を行いましょう。「何が炎上の原因になったのか」「ユーザーはどのように批判しているのか」「炎上の規模はどのくらいか」といった部分を見極めます。方針を定めてから謝罪
状況を確認できたら、それを判断材料に今後の方針を定めます。途中でコロコロ発言内容などを変えると、不誠実な印象を与えますので、一貫した態度を貫くことが大切です。
少しでも自社の方に非がある場合は、謝罪をしておいたほうが賢明だと言えます。謝罪の文書には、再発防止のための対策なども含めると誠実さ・反省の色が感じられて効果的です。場合によっては何もせず沈静化を待つ
多くの炎上は72時間以内に鎮火すると言われています。自社に非がない場合は何もせずに収まるまで待ちましょう。
例えば、ユーザー間で意見が対立している場合などは、たとえ謝罪であっても公式アカウントが片方の立場で発言をしてしまうと、かえって火に油を注いでしまうことになります。対応が必要なもの、不必要なものの判断基準もしっかり定めておくといいでしょう。まとめ
SNS時代において、どのような企業であっても炎上は起こり得るものです。そのため、予防や鎮静化のための体制を構築するといった炎上対策は、すべての会社に必要なことだと言えます。
一度炎上が起こると、企業にとって甚大なダメージを負うことになりますので、きちんと運用ルールを定めた上でSNSを利用していくようにしましょう。
-
-

-
ノーコード開発について
-

ビジネスにおけるITシステムやツールを利用する必要性が高まっている一方で、IT人材の不足に悩んでいる企業も多くなっています。
そうしたなか、Webサービスやアプリケーション、システムなどの開発手法として注目を集めているのが、「ノーコード開発」です。
今回はノーコード開発とは、メリットやデメリットはなんなのかについてご紹介していきたいと思います。ノーコード開発とは
「ノーコード開発」とは、ソースコードを記述することなく、Webサービスやアプリケーション、システムなどを開発する手法のことです。
また、ノーコードで構築・開発可能なサービスを指して、「ノーコードツール」と呼ぶこともあります。通常、Webサービスやアプリケーション、システムなどは、プログラミング言語でソースコードを記述(コーディング)して開発を行います。
一方、ノーコードツールは、ドラッグ&ドロップやマウスクリックなどの簡単な操作や文字入力など、画面上で操作が完結する「GUI(Graphical User Interface/グラフィカルユーザインターフェース)」で直感的に開発を進めることができます。プログラミングに関する専門知識がなくても開発可能なので、エンジニア以外の非IT人材でも簡単に開発を行える点が特徴です。
ノーコードツールが注目を集める理由
IT人材の不足
プログラミング言語を使い、コーディングを行うITエンジニアは主にIT企業で雇用されているため、IT企業以外の一般企業は、ITに詳しい人材を社内で確保できずに、社外で補っているところが多いでしょう。
今後ますますIT人材不足が深刻化すると予想されるなか、ITに関する専門知識を必要としないノーコードツールへの注目が高まっているのです。DXの活発化
近年、グローバル化に伴う市場競争の激化や、消費者ニーズの目まぐるしい変化に対応するため、DXの必要性が急速に高まってきています。
とくに日本企業は労働生産性の低さが指摘されており、DXによって生産性を高める取り組みが必要となっています。
しかし、DXの推進にはITシステムの活用によるデジタル化が不可欠ですが、IT人材が不足している企業においてはデジタル化の取り組みが停滞してしまいがちです。
そうしたなか、専門知識を持たない非IT人材でも対応可能なノーコードツールが注目を集めているのです。クラウドサービスの普及
従来、システム導入と言えば自社サーバーで構築・運用を行うオンプレミス型のシステムが主流でしたが、近年はインターネットを介して利用するクラウド型のシステムが普及しています。
クラウドサービスがビジネスシーンに広く浸透したことで、クラウドサービスとして提供されることが多いノーコードツールが受け入れられる状況になってきたのもノーコードツールが注目されてきている理由のひとつだと思われます。ノーコードツールのメリット・デメリット
ノーコードツールのメリット
①専門知識を必要としない
ノーコードツールの最大のメリットは、専門知識が無くても開発を行えることです。
業種・業界によっては、社内にITに精通した人材がいないことも珍しくありません。とくに、IT人材不足が深刻化している昨今、プログラミングスキルを有する人材の確保に難航してしまうケースも考えられます。
そのような企業がシステム導入を検討する際、専門知識の有無を問わないノーコードツールは魅力的な選択肢となるでしょう。②開発・運用コストの削減
開発・運用コストの削減につなげられる点も、ノーコードツールのメリットと言えます。
先述のように、ノーコードツールであれば専門知識を持たない人材でも開発を行うことが可能です。また、軽微なメンテナンスや多少の改修であれば、利用者自身で対応することができます。
そのため、システムの開発や運用などを外部に委託することなく、社内のリソースで対応することができ、コストを抑えることができます。③開発スピードの速さ
通常、システム開発を行う際は、現場担当者が必要な機能に関する要望をまとめ、システムエンジニア(SE)が要件定義やシステムの設計を行い、プログラマー(PG)がコーディング作業を行い実装していく、という流れが一般的です。
一方、ノーコードツールであればコーディングの必要がなく、専門知識を持たない現場担当者でも自ら開発を進めることができるため、従来よりもスピーディーに開発を進めることができるでしょう。ノーコードツールのデメリット
①カスタマイズに制限がある
ノーコードツールのデメリットとして、カスタマイズに制限があるという点を挙げることができます。
ノーコードツールでは、元から用意されているテンプレートや機能、オプションを組み合わせてシステムを開発していきます。
そのため、自社の要望にあわせて独自にカスタマイズすることは難しく、通常と比較するとカスタマイズの自由度は劣ってしまいます。
大規模開発や複雑な開発には対応できないケースもあるため、ツール選定の際には自社が望む開発を実現可能かあらかじめ確認しておくことが重要です。②プラットフォームへの依存が大きい
ノーコードツールでの開発は、使用しているプラットフォームが終了してしまった場合、開発したシステムを利用できなくなってしまう恐れがあります。
また、ノーコードツールは国外企業が提供している場合が多く、日本語でのサポートに対応していないケースや、利用方法に関するアドバイスやトラブルシューティングのための情報収集に苦戦してしまうことも考えられます。まとめ
専門知識を必要とせず、スピーディーかつコストを抑えてシステムやアプリケーションを開発できるノーコードツールは、今後ますます普及することが見込まれます。
ノーコード開発可能なシステム・ツールを利用して、業務効率化やDXの促進をしたいと思われた際には、ぜひアイサポートまでご連絡ください。
-
-

-
詐欺サイト・偽サイトの見分け方
-

インターネットショッピングが以前にも増して普及している中で、詐欺サイトやフィッシングサイトによる被害も多くなっています。
インターネットが普及し始めた頃から問題となっているオンラインでの詐欺は手口がどんどんと巧妙化されていて、どれだけ注意喚起されても未だに被害が無くなりません。
今回は詐欺サイト・偽サイトの見分け方や万が一購入してしまった際の対処法などをご紹介していきたいと思います。詐欺サイト・偽サイトについて
急増している詐欺サイトは大手ECサイトに偽装されたものが多く存在します。
不自然な日本語や不審な会社概要を載せている詐欺サイトはほとんど見なくなり、偽のECサイトを見分けるのが以前よりも難しく、普段からネットショッピングを利用される方も、巧妙に作り込まれた偽サイトの被害に遭ってしまう可能性があります。
詐欺サイトで商品を購入すると、注文したものと異なる商品が届いたり、商品は届かず代金だけが請求されたりします。
また、詐欺サイトで得た個人情報が不正利用され、金融機関などを騙ったなりすましメールの被害も確認されています。こういった詐欺サイトは、なりすましメールから誘導されることが多くあります。
「アカウントがロックされました」といったメールや頼んだ覚えのない注文メールが届いても、記載されているURLに安易にアクセスしないように注意してください。詐欺サイト・偽サイトの見分け方
新しいショッピングサイトを利用する際は、信用できるサイトかどうかきちんと確認することが大切です。
注意して見るべきポイントをいくつか紹介いたします。
ポイントに該当するからといって全てが詐欺サイトであるとは限りませんが、十分注意して利用することで不要なトラブルに巻き込まれないようにしましょう。サイトのURLに怪しい点がないかチェックする
URLの左端に「鍵マーク」がついていない、「https://~」で始まっていないというサイトは通信が暗号化されていません。また、URLの終わりが「.top」「.xyz」「.bid」など見慣れないものの場合も注意が必要です。
会社の概要、販売者の情報をチェックする
初めて利用するショップの場合は、会社の概要や販売元といった販売者情報を確認するように心がけましょう。
所在地や電話番号、他の利用者の評価などを自分でしっかりと確認することが重要です。
電話番号が記載されている場合には、実際に電話をかけてみてもいいかもしれません。連絡先メールアドレスの末尾があまり見ないものである場合も注意が必要です。店舗ロゴと販売商品をチェックする
例えば、商品の販売を行っている店舗名が「●●雑貨店」であるにも関わらず、「カー用品」の販売を行っているなどあまりにも関係ない商品を取り扱っている場合は気をつけましょう。
また、一般的な販売価格よりも極端に安く販売されている場合はコピー商品か、詐欺的サイトである可能性があるため注意が必要です。決済方法をチェックする
代金の支払い方法として、銀行振込しか選択できず、クレジットカードや代引きがなどの決済方法が選べない場合も気をつけなければなりません。
支払方法の説明ページでは対応するカード会社が表示されていても、実際の決済画面ではクレジットカード払いに対応していないといったケースも存在するようです。万が一購入してしまった際の対処法
万が一、詐欺サイトで買い物をしてしまい、支払いを行ってしまった場合には、すぐに販売業者に連絡をして返金の手続きを行いましょう。
それでも問題を解決できない場合には、以下の方法で対応することで、お金を取り戻すことができます。銀行振込で支払いを行った場合
銀行振込で支払いを行った場合には、振込先の口座がある金融機関の窓口へ相談・通報しましょう。
その上で、警察署に被害届を提出すると、詐欺業者の口座が凍結され、一定期間後に返金の手続きが開始されます。クレジットカードで支払いを行った場合
クレジットカードで支払いをしていた場合、条件によって支払いを拒否できる制度があります。
使用したクレジットカード、購入日時がわかるもの、メールなどの通信記録、業者やサイトの名前を確認した上で早急にカード会社へ連絡をしましょう。まとめ
詐欺サイト・偽サイトの被害は年々巧妙化しており、必ず防げる対策はありません。
しかし、詐欺サイト・偽サイトの手口を把握し、日頃から対策を行うことで被害を最小限に抑えられる可能性が高まります。
まずはしっかりとした知識を身につけるとともに、事前に被害に遭ってしまった際の対応策について確認しておきましょう。
-
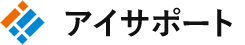
![0120-188-632 [営業時間] 9:00~18:00 [定休日} 土日祝](https://www.is1.co.jp/images/head_cont.gif?v=20210630)